
蝿のはなし
むかし、むかし、京の都に店を構える商人(あきんど)がおりました。たまという女中が5年ほどそこで働いていました。たまはいつも古い色あせた仕事着を着ていましたが、いつも陰日なたなく働いていました。
あと数日で正月を迎えるという日に、主は、よく働いた褒美として新しい着物を買うようにと娘にお金を渡しました。しかし女中は正月になっても相変わらず仕事着のままでした。
「どうしてお前は新しい着物を着ないのだ。」主は女中に尋ねました。
女中は顔を赤らめ、いんぎんに答えました。
「どうかご無礼お許し下さい。実は、頂いたお金は着物を買わずに、貯めております。私が小さいころ、ふた親が亡くなりました。一人っ子でしたので、法事をするのは私の役目と思っておりました。でも当時は、法事をするお金を工面することはできませんでした。
そこでお金を貯めて檀那寺に父母の位牌をおさめ法事をしていただこうと心に決めました。私のことをみなりの小汚い(こぎたな)い女とお思いでしょうが、やっと百文貯まりました。
主は、女中の話にいたく心を打たれ、親孝行を褒めてやりました。
ようやく女中は寺で法事を営むことができました。百文のうち七十文をその費用にあて、残りの三十文をおかみさんに預けました。
ところが、悲しいことに、翌年一月、たまは突然の病で帰らぬ人となってしまいました。
十日ばかりしたころ、大きな蝿が一匹、家の中に飛び込んできて、商人の頭の上を回り始めました。冬に蝿を見るのはめずらしいことでした。その蝿はどこにも行かないで、頭上をくるくる回り続けました。
商人は信心深かったので、蝿を殺さず、そっと捕まえると外に出してやりました。しかし蝿はすぐ戻って来ました。何度も何度も捕まえては追い出しましたが、その度に戻ってきては頭上を飛び回りました。
女房も奇妙に感じて夫に言いました。
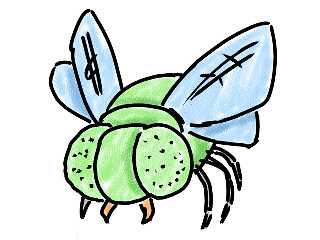 「もしかしたら、たまじゃないかしら。亡くなった者の魂がが時には虫の姿になってこの世に戻って来ると言いますから。」
「じゃ、羽根に目印の紅を入れて外に放してやろう。」
主人は、蝿を遠い所に持って行きました。
次の日、その蝿は迷うことなく家に戻って来ました。二人はもう疑いませんでした。
「たまに違いない。あの子は私たちに何かしてもらいたいに違いない。だが、一体何をしてもらいたいんだ。」
「あの子から三十文預かっています。あの子は、あのお金で自分の供養を寺でしてもらいたいのかも知れません。」
そう言うと、蝿は飛び回るのを止め、畳の上にぱたりと落ち、死んでしまいました。
夫婦はすぐに小箱に蝿を入れて寺にもって行き、三十文払って供養をしてもらいました。
蝿の死骸を収めた箱は、寺の境内に埋められ、その上に卒塔婆が建てられました。
「もしかしたら、たまじゃないかしら。亡くなった者の魂がが時には虫の姿になってこの世に戻って来ると言いますから。」
「じゃ、羽根に目印の紅を入れて外に放してやろう。」
主人は、蝿を遠い所に持って行きました。
次の日、その蝿は迷うことなく家に戻って来ました。二人はもう疑いませんでした。
「たまに違いない。あの子は私たちに何かしてもらいたいに違いない。だが、一体何をしてもらいたいんだ。」
「あの子から三十文預かっています。あの子は、あのお金で自分の供養を寺でしてもらいたいのかも知れません。」
そう言うと、蝿は飛び回るのを止め、畳の上にぱたりと落ち、死んでしまいました。
夫婦はすぐに小箱に蝿を入れて寺にもって行き、三十文払って供養をしてもらいました。
蝿の死骸を収めた箱は、寺の境内に埋められ、その上に卒塔婆が建てられました。
小泉八雲「骨董」より



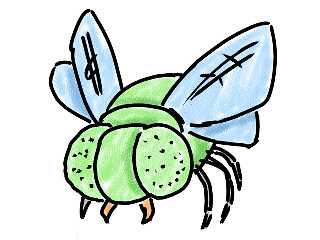 「もしかしたら、たまじゃないかしら。亡くなった者の魂がが時には虫の姿になってこの世に戻って来ると言いますから。」
「じゃ、羽根に目印の紅を入れて外に放してやろう。」
主人は、蝿を遠い所に持って行きました。
次の日、その蝿は迷うことなく家に戻って来ました。二人はもう疑いませんでした。
「たまに違いない。あの子は私たちに何かしてもらいたいに違いない。だが、一体何をしてもらいたいんだ。」
「あの子から三十文預かっています。あの子は、あのお金で自分の供養を寺でしてもらいたいのかも知れません。」
そう言うと、蝿は飛び回るのを止め、畳の上にぱたりと落ち、死んでしまいました。
夫婦はすぐに小箱に蝿を入れて寺にもって行き、三十文払って供養をしてもらいました。
蝿の死骸を収めた箱は、寺の境内に埋められ、その上に卒塔婆が建てられました。
「もしかしたら、たまじゃないかしら。亡くなった者の魂がが時には虫の姿になってこの世に戻って来ると言いますから。」
「じゃ、羽根に目印の紅を入れて外に放してやろう。」
主人は、蝿を遠い所に持って行きました。
次の日、その蝿は迷うことなく家に戻って来ました。二人はもう疑いませんでした。
「たまに違いない。あの子は私たちに何かしてもらいたいに違いない。だが、一体何をしてもらいたいんだ。」
「あの子から三十文預かっています。あの子は、あのお金で自分の供養を寺でしてもらいたいのかも知れません。」
そう言うと、蝿は飛び回るのを止め、畳の上にぱたりと落ち、死んでしまいました。
夫婦はすぐに小箱に蝿を入れて寺にもって行き、三十文払って供養をしてもらいました。
蝿の死骸を収めた箱は、寺の境内に埋められ、その上に卒塔婆が建てられました。
