
羊太夫伝説
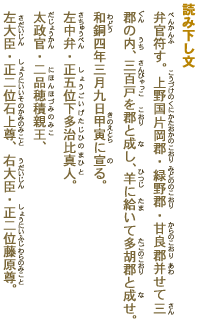 どこか群馬の地に足を運べば、きっと「多胡碑」のことを耳にするでしょう。それは群馬の小さい町、多胡郡(現高崎市)吉井町にあります。実は日本三古碑の一つでもあります。その碑文には多野郡のいわれが漢字で刻まれています。漢字の中に「羊」という文字があります。「羊」は、八世紀初頭、朝廷より郡司(郡の長)としてこの地を治めることを命ぜられた人物と言われています。これは、その「羊」にまつわる伝説です。
その人物は、(旧暦の)羊(ひつじ)の日、羊の刻に生まれたことから「羊」という名前がついたそうです。やがて背の高い、才能ある若者に成長しました。
711年(和銅4年)多胡郡司を命ぜられたので、「羊」は大和の国(現奈良県)の朝廷を定期的に訪れることになりました。「羊」には、駿馬(しゅんめ)と、「小脛(こはぎ)」と言う忠実な家来がおりました。その馬と「小脛」の走りにかなう馬はどこにもおりませんでした。何しろ二日もあれば難なく朝廷に行ってまた戻ってこられるのですから。
「羊」は優れた能力を持ち、忠実な働きぶりでしたから、天皇から大きな信頼を受けていました。誠実な心で那(くに)を治めるので、人々から「羊太夫」と呼ばれていました。
ある日のこと、朝廷に向かう途中、「羊太夫」一行はいつものように休息しました。「小脛」は自分の寝姿は絶対見ないよう主(あるじ)にお願いして、どこかに消えてしまいました。好奇心にかられた「羊太夫」はこっそり後をつけて、大きな木の陰で寝ている「小脛」を見つけました。地面に横たわっている「小脛」を頭のてっぺんからつま先までを見回しましたが、これと言って変わった所はありません。ほっとしましたが、もう一度よく見てみました。すると「小脛」のわきの下に羽が生えているではありませんか。
「何だ、これは。」ものめずらしさから一本ずつ抜いてみました。面白半分にしたことですが、それがよもやとんでもない事態を招くとは思っても見ませんでした。「小脛」はじきに目を覚まし、主がしたことに気づきました。「小脛」は唖然(あぜん)とし、やがて悲しくなりました。
「あの羽は私の守り神でした。馬と一緒に速く走れたのも、あの羽があったからこそです。羽がなくては、もう速く走ることはできません。馬だってもう速く走ることはできません。これから不吉なことが起こらなければよいのですが。」
「小脛」が言ったとおり、彼も馬も速く走れなくなり、「羊太夫」は今までのように頻繁に朝廷に参内し、仕えることができなくなりましたが、このことが災いをもたらすとは、ゆめゆめ思いませんでした。
朝廷の廷臣のなかには、「羊太夫」の才能をうらやむ者がいたのでしょう。「羊太夫」が朝廷に謀反を企て、攻撃の準備をしているといううわさが流れました。まもなく朝廷は多胡に大軍を送り込みました。「羊太夫」は想像以上に事態が悪化していることを悟りましたが、争うことだけは避けたいことでした。「羊太夫」は朝廷軍が陣をとっている地を訪れ、忠節の心を示し、戦いを回避しようとしました。
「羊太夫」は朝廷軍の大将に言いました。
どこか群馬の地に足を運べば、きっと「多胡碑」のことを耳にするでしょう。それは群馬の小さい町、多胡郡(現高崎市)吉井町にあります。実は日本三古碑の一つでもあります。その碑文には多野郡のいわれが漢字で刻まれています。漢字の中に「羊」という文字があります。「羊」は、八世紀初頭、朝廷より郡司(郡の長)としてこの地を治めることを命ぜられた人物と言われています。これは、その「羊」にまつわる伝説です。
その人物は、(旧暦の)羊(ひつじ)の日、羊の刻に生まれたことから「羊」という名前がついたそうです。やがて背の高い、才能ある若者に成長しました。
711年(和銅4年)多胡郡司を命ぜられたので、「羊」は大和の国(現奈良県)の朝廷を定期的に訪れることになりました。「羊」には、駿馬(しゅんめ)と、「小脛(こはぎ)」と言う忠実な家来がおりました。その馬と「小脛」の走りにかなう馬はどこにもおりませんでした。何しろ二日もあれば難なく朝廷に行ってまた戻ってこられるのですから。
「羊」は優れた能力を持ち、忠実な働きぶりでしたから、天皇から大きな信頼を受けていました。誠実な心で那(くに)を治めるので、人々から「羊太夫」と呼ばれていました。
ある日のこと、朝廷に向かう途中、「羊太夫」一行はいつものように休息しました。「小脛」は自分の寝姿は絶対見ないよう主(あるじ)にお願いして、どこかに消えてしまいました。好奇心にかられた「羊太夫」はこっそり後をつけて、大きな木の陰で寝ている「小脛」を見つけました。地面に横たわっている「小脛」を頭のてっぺんからつま先までを見回しましたが、これと言って変わった所はありません。ほっとしましたが、もう一度よく見てみました。すると「小脛」のわきの下に羽が生えているではありませんか。
「何だ、これは。」ものめずらしさから一本ずつ抜いてみました。面白半分にしたことですが、それがよもやとんでもない事態を招くとは思っても見ませんでした。「小脛」はじきに目を覚まし、主がしたことに気づきました。「小脛」は唖然(あぜん)とし、やがて悲しくなりました。
「あの羽は私の守り神でした。馬と一緒に速く走れたのも、あの羽があったからこそです。羽がなくては、もう速く走ることはできません。馬だってもう速く走ることはできません。これから不吉なことが起こらなければよいのですが。」
「小脛」が言ったとおり、彼も馬も速く走れなくなり、「羊太夫」は今までのように頻繁に朝廷に参内し、仕えることができなくなりましたが、このことが災いをもたらすとは、ゆめゆめ思いませんでした。
朝廷の廷臣のなかには、「羊太夫」の才能をうらやむ者がいたのでしょう。「羊太夫」が朝廷に謀反を企て、攻撃の準備をしているといううわさが流れました。まもなく朝廷は多胡に大軍を送り込みました。「羊太夫」は想像以上に事態が悪化していることを悟りましたが、争うことだけは避けたいことでした。「羊太夫」は朝廷軍が陣をとっている地を訪れ、忠節の心を示し、戦いを回避しようとしました。
「羊太夫」は朝廷軍の大将に言いました。
 「ご存知のとおり、私は忠義、忠誠を重んじております。朝廷に叛(そむ)く気は毛頭ございません。この地の民は皆思いやりがあり、穏やかです。労を惜しまず、争いは好みません。たとえ勝ったとしても、この戦いで私の郡司としての力はなくなることでしょう。是が非でも争いは避けたいと思っております。このまま戻って天皇さまにお伝え願いたい。」
大将は羊太夫に耳を傾け、言いました。
「そなたが言うことはわかりました。そなたが今も変わらず忠実であることは承知しております。しかし、羊太夫を亡き者にせよ、との天皇様のご命令です。ご命令はご命令です。ご命令に背くわけにはいきません。どちらかが誉れ高く滅びるまで果断に戦おうではありませんか。」
「羊太夫」は膠着(こうちゃく)状態を打破するすべはないと知り、死を覚悟しました。彼は意を決して言いました。
「私は心を決めました。精一杯あなたと戦います。あなたが勝利を収め、朝廷に戻った暁(あかつき)には、天皇に、私が誓って間違ったことはしていない、と申していたとお伝え下さい。是非お願いします。」
戦いの火蓋が切られました。朝廷軍の圧倒的な兵の数に対し、「羊太夫」にはわずか数百の兵しかおりません。ついに兵と一族は城に追い込まれてしまいました。
「ご存知のとおり、私は忠義、忠誠を重んじております。朝廷に叛(そむ)く気は毛頭ございません。この地の民は皆思いやりがあり、穏やかです。労を惜しまず、争いは好みません。たとえ勝ったとしても、この戦いで私の郡司としての力はなくなることでしょう。是が非でも争いは避けたいと思っております。このまま戻って天皇さまにお伝え願いたい。」
大将は羊太夫に耳を傾け、言いました。
「そなたが言うことはわかりました。そなたが今も変わらず忠実であることは承知しております。しかし、羊太夫を亡き者にせよ、との天皇様のご命令です。ご命令はご命令です。ご命令に背くわけにはいきません。どちらかが誉れ高く滅びるまで果断に戦おうではありませんか。」
「羊太夫」は膠着(こうちゃく)状態を打破するすべはないと知り、死を覚悟しました。彼は意を決して言いました。
「私は心を決めました。精一杯あなたと戦います。あなたが勝利を収め、朝廷に戻った暁(あかつき)には、天皇に、私が誓って間違ったことはしていない、と申していたとお伝え下さい。是非お願いします。」
戦いの火蓋が切られました。朝廷軍の圧倒的な兵の数に対し、「羊太夫」にはわずか数百の兵しかおりません。ついに兵と一族は城に追い込まれてしまいました。
 「羊太夫」は家来に言いました。
「女、子どもをこの城から出しなさい。生き延びてもらいたい。悲しんでいる場合ではない。急ぎなさい!残念ながら、この戦いに、もはや勝利するすべはない。死するは覚悟の上。さあ行きなさい!」
熾烈(しれつ)を極めた戦いで、羊太夫の兵は全員命を落とし、残ったのは「羊太夫」と「小脛」のみでした。
「小脛」は主(あるじ)に言いました。
「羊太夫様、ここで生き残っているのはわれらだけです。」
「わかっておる。われらにもそろそろ旅立ちの時が来たようだ。」羊太夫は重々しく言いました。
すると羊太夫の鎧(よろい)と兜(かぶと)が二つに割れ、彼の体が変わり始めました。頭と体は羽毛に覆われ、手は翼に変わり、脚は細くなり、つま先には鋭い爪が生え、口には嘴(くちばし)が。まさに同じことが「小脛」にも起こっていました。二人(二羽)はチラッと眼を合わせると、鋭い声をあげ、翼を羽ばたかせ、飛び去りました。
その日の午後、二羽の鳶(とび)が山の方に向かって飛んで行くの見た、と多くの民が話していました。
後に、この地に多胡碑が建てられました。人々は今でも多胡碑を「ひつじさま」と呼んであがめているということです。(kudos)
(資料及び画像:高崎市吉井町より)
「羊太夫」は家来に言いました。
「女、子どもをこの城から出しなさい。生き延びてもらいたい。悲しんでいる場合ではない。急ぎなさい!残念ながら、この戦いに、もはや勝利するすべはない。死するは覚悟の上。さあ行きなさい!」
熾烈(しれつ)を極めた戦いで、羊太夫の兵は全員命を落とし、残ったのは「羊太夫」と「小脛」のみでした。
「小脛」は主(あるじ)に言いました。
「羊太夫様、ここで生き残っているのはわれらだけです。」
「わかっておる。われらにもそろそろ旅立ちの時が来たようだ。」羊太夫は重々しく言いました。
すると羊太夫の鎧(よろい)と兜(かぶと)が二つに割れ、彼の体が変わり始めました。頭と体は羽毛に覆われ、手は翼に変わり、脚は細くなり、つま先には鋭い爪が生え、口には嘴(くちばし)が。まさに同じことが「小脛」にも起こっていました。二人(二羽)はチラッと眼を合わせると、鋭い声をあげ、翼を羽ばたかせ、飛び去りました。
その日の午後、二羽の鳶(とび)が山の方に向かって飛んで行くの見た、と多くの民が話していました。
後に、この地に多胡碑が建てられました。人々は今でも多胡碑を「ひつじさま」と呼んであがめているということです。(kudos)
(資料及び画像:高崎市吉井町より)



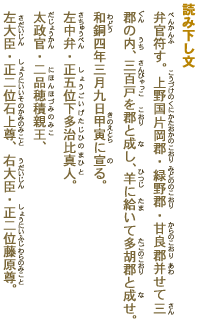 どこか群馬の地に足を運べば、きっと「多胡碑」のことを耳にするでしょう。それは群馬の小さい町、多胡郡(現高崎市)吉井町にあります。実は日本三古碑の一つでもあります。その碑文には多野郡のいわれが漢字で刻まれています。漢字の中に「羊」という文字があります。「羊」は、八世紀初頭、朝廷より郡司(郡の長)としてこの地を治めることを命ぜられた人物と言われています。これは、その「羊」にまつわる伝説です。
その人物は、(旧暦の)羊(ひつじ)の日、羊の刻に生まれたことから「羊」という名前がついたそうです。やがて背の高い、才能ある若者に成長しました。
711年(和銅4年)多胡郡司を命ぜられたので、「羊」は大和の国(現奈良県)の朝廷を定期的に訪れることになりました。「羊」には、駿馬(しゅんめ)と、「小脛(こはぎ)」と言う忠実な家来がおりました。その馬と「小脛」の走りにかなう馬はどこにもおりませんでした。何しろ二日もあれば難なく朝廷に行ってまた戻ってこられるのですから。
「羊」は優れた能力を持ち、忠実な働きぶりでしたから、天皇から大きな信頼を受けていました。誠実な心で那(くに)を治めるので、人々から「羊太夫」と呼ばれていました。
ある日のこと、朝廷に向かう途中、「羊太夫」一行はいつものように休息しました。「小脛」は自分の寝姿は絶対見ないよう主(あるじ)にお願いして、どこかに消えてしまいました。好奇心にかられた「羊太夫」はこっそり後をつけて、大きな木の陰で寝ている「小脛」を見つけました。地面に横たわっている「小脛」を頭のてっぺんからつま先までを見回しましたが、これと言って変わった所はありません。ほっとしましたが、もう一度よく見てみました。すると「小脛」のわきの下に羽が生えているではありませんか。
「何だ、これは。」ものめずらしさから一本ずつ抜いてみました。面白半分にしたことですが、それがよもやとんでもない事態を招くとは思っても見ませんでした。「小脛」はじきに目を覚まし、主がしたことに気づきました。「小脛」は唖然(あぜん)とし、やがて悲しくなりました。
「あの羽は私の守り神でした。馬と一緒に速く走れたのも、あの羽があったからこそです。羽がなくては、もう速く走ることはできません。馬だってもう速く走ることはできません。これから不吉なことが起こらなければよいのですが。」
「小脛」が言ったとおり、彼も馬も速く走れなくなり、「羊太夫」は今までのように頻繁に朝廷に参内し、仕えることができなくなりましたが、このことが災いをもたらすとは、ゆめゆめ思いませんでした。
朝廷の廷臣のなかには、「羊太夫」の才能をうらやむ者がいたのでしょう。「羊太夫」が朝廷に謀反を企て、攻撃の準備をしているといううわさが流れました。まもなく朝廷は多胡に大軍を送り込みました。「羊太夫」は想像以上に事態が悪化していることを悟りましたが、争うことだけは避けたいことでした。「羊太夫」は朝廷軍が陣をとっている地を訪れ、忠節の心を示し、戦いを回避しようとしました。
「羊太夫」は朝廷軍の大将に言いました。
どこか群馬の地に足を運べば、きっと「多胡碑」のことを耳にするでしょう。それは群馬の小さい町、多胡郡(現高崎市)吉井町にあります。実は日本三古碑の一つでもあります。その碑文には多野郡のいわれが漢字で刻まれています。漢字の中に「羊」という文字があります。「羊」は、八世紀初頭、朝廷より郡司(郡の長)としてこの地を治めることを命ぜられた人物と言われています。これは、その「羊」にまつわる伝説です。
その人物は、(旧暦の)羊(ひつじ)の日、羊の刻に生まれたことから「羊」という名前がついたそうです。やがて背の高い、才能ある若者に成長しました。
711年(和銅4年)多胡郡司を命ぜられたので、「羊」は大和の国(現奈良県)の朝廷を定期的に訪れることになりました。「羊」には、駿馬(しゅんめ)と、「小脛(こはぎ)」と言う忠実な家来がおりました。その馬と「小脛」の走りにかなう馬はどこにもおりませんでした。何しろ二日もあれば難なく朝廷に行ってまた戻ってこられるのですから。
「羊」は優れた能力を持ち、忠実な働きぶりでしたから、天皇から大きな信頼を受けていました。誠実な心で那(くに)を治めるので、人々から「羊太夫」と呼ばれていました。
ある日のこと、朝廷に向かう途中、「羊太夫」一行はいつものように休息しました。「小脛」は自分の寝姿は絶対見ないよう主(あるじ)にお願いして、どこかに消えてしまいました。好奇心にかられた「羊太夫」はこっそり後をつけて、大きな木の陰で寝ている「小脛」を見つけました。地面に横たわっている「小脛」を頭のてっぺんからつま先までを見回しましたが、これと言って変わった所はありません。ほっとしましたが、もう一度よく見てみました。すると「小脛」のわきの下に羽が生えているではありませんか。
「何だ、これは。」ものめずらしさから一本ずつ抜いてみました。面白半分にしたことですが、それがよもやとんでもない事態を招くとは思っても見ませんでした。「小脛」はじきに目を覚まし、主がしたことに気づきました。「小脛」は唖然(あぜん)とし、やがて悲しくなりました。
「あの羽は私の守り神でした。馬と一緒に速く走れたのも、あの羽があったからこそです。羽がなくては、もう速く走ることはできません。馬だってもう速く走ることはできません。これから不吉なことが起こらなければよいのですが。」
「小脛」が言ったとおり、彼も馬も速く走れなくなり、「羊太夫」は今までのように頻繁に朝廷に参内し、仕えることができなくなりましたが、このことが災いをもたらすとは、ゆめゆめ思いませんでした。
朝廷の廷臣のなかには、「羊太夫」の才能をうらやむ者がいたのでしょう。「羊太夫」が朝廷に謀反を企て、攻撃の準備をしているといううわさが流れました。まもなく朝廷は多胡に大軍を送り込みました。「羊太夫」は想像以上に事態が悪化していることを悟りましたが、争うことだけは避けたいことでした。「羊太夫」は朝廷軍が陣をとっている地を訪れ、忠節の心を示し、戦いを回避しようとしました。
「羊太夫」は朝廷軍の大将に言いました。
 「ご存知のとおり、私は忠義、忠誠を重んじております。朝廷に叛(そむ)く気は毛頭ございません。この地の民は皆思いやりがあり、穏やかです。労を惜しまず、争いは好みません。たとえ勝ったとしても、この戦いで私の郡司としての力はなくなることでしょう。是が非でも争いは避けたいと思っております。このまま戻って天皇さまにお伝え願いたい。」
大将は羊太夫に耳を傾け、言いました。
「そなたが言うことはわかりました。そなたが今も変わらず忠実であることは承知しております。しかし、羊太夫を亡き者にせよ、との天皇様のご命令です。ご命令はご命令です。ご命令に背くわけにはいきません。どちらかが誉れ高く滅びるまで果断に戦おうではありませんか。」
「羊太夫」は膠着(こうちゃく)状態を打破するすべはないと知り、死を覚悟しました。彼は意を決して言いました。
「私は心を決めました。精一杯あなたと戦います。あなたが勝利を収め、朝廷に戻った暁(あかつき)には、天皇に、私が誓って間違ったことはしていない、と申していたとお伝え下さい。是非お願いします。」
戦いの火蓋が切られました。朝廷軍の圧倒的な兵の数に対し、「羊太夫」にはわずか数百の兵しかおりません。ついに兵と一族は城に追い込まれてしまいました。
「ご存知のとおり、私は忠義、忠誠を重んじております。朝廷に叛(そむ)く気は毛頭ございません。この地の民は皆思いやりがあり、穏やかです。労を惜しまず、争いは好みません。たとえ勝ったとしても、この戦いで私の郡司としての力はなくなることでしょう。是が非でも争いは避けたいと思っております。このまま戻って天皇さまにお伝え願いたい。」
大将は羊太夫に耳を傾け、言いました。
「そなたが言うことはわかりました。そなたが今も変わらず忠実であることは承知しております。しかし、羊太夫を亡き者にせよ、との天皇様のご命令です。ご命令はご命令です。ご命令に背くわけにはいきません。どちらかが誉れ高く滅びるまで果断に戦おうではありませんか。」
「羊太夫」は膠着(こうちゃく)状態を打破するすべはないと知り、死を覚悟しました。彼は意を決して言いました。
「私は心を決めました。精一杯あなたと戦います。あなたが勝利を収め、朝廷に戻った暁(あかつき)には、天皇に、私が誓って間違ったことはしていない、と申していたとお伝え下さい。是非お願いします。」
戦いの火蓋が切られました。朝廷軍の圧倒的な兵の数に対し、「羊太夫」にはわずか数百の兵しかおりません。ついに兵と一族は城に追い込まれてしまいました。
 「羊太夫」は家来に言いました。
「女、子どもをこの城から出しなさい。生き延びてもらいたい。悲しんでいる場合ではない。急ぎなさい!残念ながら、この戦いに、もはや勝利するすべはない。死するは覚悟の上。さあ行きなさい!」
熾烈(しれつ)を極めた戦いで、羊太夫の兵は全員命を落とし、残ったのは「羊太夫」と「小脛」のみでした。
「小脛」は主(あるじ)に言いました。
「羊太夫様、ここで生き残っているのはわれらだけです。」
「わかっておる。われらにもそろそろ旅立ちの時が来たようだ。」羊太夫は重々しく言いました。
すると羊太夫の鎧(よろい)と兜(かぶと)が二つに割れ、彼の体が変わり始めました。頭と体は羽毛に覆われ、手は翼に変わり、脚は細くなり、つま先には鋭い爪が生え、口には嘴(くちばし)が。まさに同じことが「小脛」にも起こっていました。二人(二羽)はチラッと眼を合わせると、鋭い声をあげ、翼を羽ばたかせ、飛び去りました。
その日の午後、二羽の鳶(とび)が山の方に向かって飛んで行くの見た、と多くの民が話していました。
後に、この地に多胡碑が建てられました。人々は今でも多胡碑を「ひつじさま」と呼んであがめているということです。(kudos)
(資料及び画像:高崎市吉井町より)
「羊太夫」は家来に言いました。
「女、子どもをこの城から出しなさい。生き延びてもらいたい。悲しんでいる場合ではない。急ぎなさい!残念ながら、この戦いに、もはや勝利するすべはない。死するは覚悟の上。さあ行きなさい!」
熾烈(しれつ)を極めた戦いで、羊太夫の兵は全員命を落とし、残ったのは「羊太夫」と「小脛」のみでした。
「小脛」は主(あるじ)に言いました。
「羊太夫様、ここで生き残っているのはわれらだけです。」
「わかっておる。われらにもそろそろ旅立ちの時が来たようだ。」羊太夫は重々しく言いました。
すると羊太夫の鎧(よろい)と兜(かぶと)が二つに割れ、彼の体が変わり始めました。頭と体は羽毛に覆われ、手は翼に変わり、脚は細くなり、つま先には鋭い爪が生え、口には嘴(くちばし)が。まさに同じことが「小脛」にも起こっていました。二人(二羽)はチラッと眼を合わせると、鋭い声をあげ、翼を羽ばたかせ、飛び去りました。
その日の午後、二羽の鳶(とび)が山の方に向かって飛んで行くの見た、と多くの民が話していました。
後に、この地に多胡碑が建てられました。人々は今でも多胡碑を「ひつじさま」と呼んであがめているということです。(kudos)
(資料及び画像:高崎市吉井町より)
