
(続)一杯のかけ蕎麦
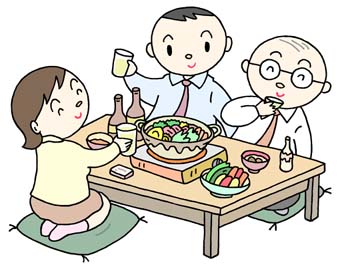 また一年が過ぎました・・・北海亭では、九時半を過ぎると、二番テーブルに「予約席」の札が置かれました。でもあの母親と二人の息子は現れませんでした。次の年も、その次の年も、三人のために二番テーブルを用意しましたが、三人は現れませんでした。
北海亭は改装され、新しいテーブルとイスに入れ替わりましたが、古びた二番テーブルとイスは昔のままに、新しいものに囲まれるように置いてありました。
「何だって、こんなところに古いテーブルとイスが置いてあるんですか?」
と不思議がる客もいました。店主と女将(おかみ)は「一杯のかけ蕎麦」の由来(ゆらい)を語り、この古いテーブルでどんなに励まされたか、三人がいつの日かやって来たら、このテーブルに座ってもらうのだ、と付け加えました。
「幸せのテーブル」の話は口コミで広まっていきました。実際その評判のテーブルで蕎麦を食べようと遠い所からやって来た女子校生や、「幸せのテーブル」が空くのを待って注文し直す若いカップルもいました。
数年が過ぎたある大晦日、家族同様の付き合いの店主の友人たちが仕事を終えて、次から次へと集まって来ました。
彼らにとっては、この数年来続いている年中行事でした。北海亭で、除夜の鐘を聞きながら、年越し蕎麦を食べて、仲間とその家族全員で最寄りの神社に詣でるというものでした。
九時半を過ぎ、刺し身の大皿を持って入って来た魚屋夫婦を皮切りに、三十人以上の友人たちが酒やおつまみを持ってやって来ました。店内は一気に賑(にぎ)やかになりました。
「二番テーブル」のことは誰もが知っていましたが、あの三人が今年も来ていないことは口にしませんでした。「予約席」が空いていても、誰も座らず、テーブルのそばの狭い座敷に、肩を寄せ合って座り、後から来る人のために、スペースを作っておきました。
十時過ぎ、宴はたけなわになりました。飲んだり食べたりする人、店主の料理の手伝いをしたり、冷蔵庫から何かを取り出したりする人、年末大売り出しのこと、夏に海水浴に行ったこと、孫ができたことなどを話している人、など、など・・・・。その時、入り口の戸が開きました。みんな、話を止めました。入口に目を向ける人もいました。
ジャケット姿の二人の若者が、手にコートを持って、蕎麦屋に入って来ました。溜息とともに、宴の喧騒がもとに戻りました。女将が、「すみませんが満席なので・・・・。」と二人に丁重にお断りしようとした時、着物姿の婦人が入ってきて二人の間に立ちました。みんな固唾(かたず)をのんで、耳をそばだてました。
「あの・・・かけ蕎麦・・・三つ・・・お願いできますか?」
女将は、その声を聞いてはっとしました。決して忘れられないあの記憶―――十数年前店に来た、母親と二人の息子―――が蘇りました。
女将の視線は、驚きのあまり、目を見開(みひら)いている夫と、今やって来たばかりの三人の間を、行ったり来たりしました。
「あっ・・・えーと・・・そちら・・・そちらさまは・・・」女将はとまどいながら言いました。
若者の一人が答えました。
「私たちは十四年前の大晦日に、ここで一杯のかけ蕎麦を三人で食べた母子(おやこ)です。一杯のかけ蕎麦に勇気づけられ、おかげで、三人で何とか助け合いやって来ました。その後、母の実家の滋賀県に移りましたが、今年、私は医師国家試験に合格し、研修医として京都大学付属病院で働いています。そして来年の4月からは札幌総合病院で勤務することになっています。今回、病院関係者との最初の打ち合わせと、父親の墓前報告を兼ねて札幌に来ました。弟は、蕎麦屋さんにはなりませんでしたが、京都の銀行に勤めております。人生で最高の贅沢・・・大晦日に母と一緒に北海亭に行って、かけ蕎麦を三つ注文する、ということを弟と計画しました。
若者の話を頷(うなづ)きながら聞く店主と女将の目には涙が溢(あふ)れてきました。
入口近くのテーブルで蕎麦を啜(すす)っていた八百屋のおやじさんは、蕎麦をゴクッと飲み込むと、立ち上がりました。
また一年が過ぎました・・・北海亭では、九時半を過ぎると、二番テーブルに「予約席」の札が置かれました。でもあの母親と二人の息子は現れませんでした。次の年も、その次の年も、三人のために二番テーブルを用意しましたが、三人は現れませんでした。
北海亭は改装され、新しいテーブルとイスに入れ替わりましたが、古びた二番テーブルとイスは昔のままに、新しいものに囲まれるように置いてありました。
「何だって、こんなところに古いテーブルとイスが置いてあるんですか?」
と不思議がる客もいました。店主と女将(おかみ)は「一杯のかけ蕎麦」の由来(ゆらい)を語り、この古いテーブルでどんなに励まされたか、三人がいつの日かやって来たら、このテーブルに座ってもらうのだ、と付け加えました。
「幸せのテーブル」の話は口コミで広まっていきました。実際その評判のテーブルで蕎麦を食べようと遠い所からやって来た女子校生や、「幸せのテーブル」が空くのを待って注文し直す若いカップルもいました。
数年が過ぎたある大晦日、家族同様の付き合いの店主の友人たちが仕事を終えて、次から次へと集まって来ました。
彼らにとっては、この数年来続いている年中行事でした。北海亭で、除夜の鐘を聞きながら、年越し蕎麦を食べて、仲間とその家族全員で最寄りの神社に詣でるというものでした。
九時半を過ぎ、刺し身の大皿を持って入って来た魚屋夫婦を皮切りに、三十人以上の友人たちが酒やおつまみを持ってやって来ました。店内は一気に賑(にぎ)やかになりました。
「二番テーブル」のことは誰もが知っていましたが、あの三人が今年も来ていないことは口にしませんでした。「予約席」が空いていても、誰も座らず、テーブルのそばの狭い座敷に、肩を寄せ合って座り、後から来る人のために、スペースを作っておきました。
十時過ぎ、宴はたけなわになりました。飲んだり食べたりする人、店主の料理の手伝いをしたり、冷蔵庫から何かを取り出したりする人、年末大売り出しのこと、夏に海水浴に行ったこと、孫ができたことなどを話している人、など、など・・・・。その時、入り口の戸が開きました。みんな、話を止めました。入口に目を向ける人もいました。
ジャケット姿の二人の若者が、手にコートを持って、蕎麦屋に入って来ました。溜息とともに、宴の喧騒がもとに戻りました。女将が、「すみませんが満席なので・・・・。」と二人に丁重にお断りしようとした時、着物姿の婦人が入ってきて二人の間に立ちました。みんな固唾(かたず)をのんで、耳をそばだてました。
「あの・・・かけ蕎麦・・・三つ・・・お願いできますか?」
女将は、その声を聞いてはっとしました。決して忘れられないあの記憶―――十数年前店に来た、母親と二人の息子―――が蘇りました。
女将の視線は、驚きのあまり、目を見開(みひら)いている夫と、今やって来たばかりの三人の間を、行ったり来たりしました。
「あっ・・・えーと・・・そちら・・・そちらさまは・・・」女将はとまどいながら言いました。
若者の一人が答えました。
「私たちは十四年前の大晦日に、ここで一杯のかけ蕎麦を三人で食べた母子(おやこ)です。一杯のかけ蕎麦に勇気づけられ、おかげで、三人で何とか助け合いやって来ました。その後、母の実家の滋賀県に移りましたが、今年、私は医師国家試験に合格し、研修医として京都大学付属病院で働いています。そして来年の4月からは札幌総合病院で勤務することになっています。今回、病院関係者との最初の打ち合わせと、父親の墓前報告を兼ねて札幌に来ました。弟は、蕎麦屋さんにはなりませんでしたが、京都の銀行に勤めております。人生で最高の贅沢・・・大晦日に母と一緒に北海亭に行って、かけ蕎麦を三つ注文する、ということを弟と計画しました。
若者の話を頷(うなづ)きながら聞く店主と女将の目には涙が溢(あふ)れてきました。
入口近くのテーブルで蕎麦を啜(すす)っていた八百屋のおやじさんは、蕎麦をゴクッと飲み込むと、立ち上がりました。
 「よう、お二人さん!何をもたもたしているんだよ。十年間、大晦日の十時に来る予約席のお客を待っていたんだろ。ついに来たんだよ。お客さんをテーブルに通しなよ!」
女将は、八百屋のおやじさんの肩を叩くと、気を落ち着けて、大きな声で言いました。
「いらっしゃいませ!お待ちしておりました。こちらへどうぞ。二番テーブル、かけ三丁!」
「あいよ、かけ三丁!」
店主は、いつもの無愛想な顔を涙で濡らして答えました。
蕎麦屋では、突如として一斉に拍手と喝采が湧き起こりました。
外では、ちょっと前まで降っていた粉雪も止み、新雪に映える北海亭の暖簾(のれん)が元旦の風に揺れていました。(kudos)
一杯のかけ蕎麦
「よう、お二人さん!何をもたもたしているんだよ。十年間、大晦日の十時に来る予約席のお客を待っていたんだろ。ついに来たんだよ。お客さんをテーブルに通しなよ!」
女将は、八百屋のおやじさんの肩を叩くと、気を落ち着けて、大きな声で言いました。
「いらっしゃいませ!お待ちしておりました。こちらへどうぞ。二番テーブル、かけ三丁!」
「あいよ、かけ三丁!」
店主は、いつもの無愛想な顔を涙で濡らして答えました。
蕎麦屋では、突如として一斉に拍手と喝采が湧き起こりました。
外では、ちょっと前まで降っていた粉雪も止み、新雪に映える北海亭の暖簾(のれん)が元旦の風に揺れていました。(kudos)
一杯のかけ蕎麦



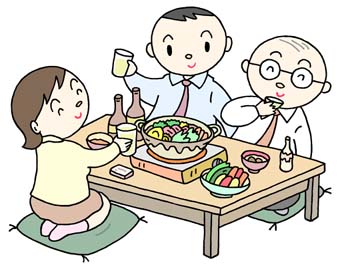 また一年が過ぎました・・・北海亭では、九時半を過ぎると、二番テーブルに「予約席」の札が置かれました。でもあの母親と二人の息子は現れませんでした。次の年も、その次の年も、三人のために二番テーブルを用意しましたが、三人は現れませんでした。
北海亭は改装され、新しいテーブルとイスに入れ替わりましたが、古びた二番テーブルとイスは昔のままに、新しいものに囲まれるように置いてありました。
「何だって、こんなところに古いテーブルとイスが置いてあるんですか?」
と不思議がる客もいました。店主と女将(おかみ)は「一杯のかけ蕎麦」の由来(ゆらい)を語り、この古いテーブルでどんなに励まされたか、三人がいつの日かやって来たら、このテーブルに座ってもらうのだ、と付け加えました。
「幸せのテーブル」の話は口コミで広まっていきました。実際その評判のテーブルで蕎麦を食べようと遠い所からやって来た女子校生や、「幸せのテーブル」が空くのを待って注文し直す若いカップルもいました。
数年が過ぎたある大晦日、家族同様の付き合いの店主の友人たちが仕事を終えて、次から次へと集まって来ました。
彼らにとっては、この数年来続いている年中行事でした。北海亭で、除夜の鐘を聞きながら、年越し蕎麦を食べて、仲間とその家族全員で最寄りの神社に詣でるというものでした。
九時半を過ぎ、刺し身の大皿を持って入って来た魚屋夫婦を皮切りに、三十人以上の友人たちが酒やおつまみを持ってやって来ました。店内は一気に賑(にぎ)やかになりました。
「二番テーブル」のことは誰もが知っていましたが、あの三人が今年も来ていないことは口にしませんでした。「予約席」が空いていても、誰も座らず、テーブルのそばの狭い座敷に、肩を寄せ合って座り、後から来る人のために、スペースを作っておきました。
十時過ぎ、宴はたけなわになりました。飲んだり食べたりする人、店主の料理の手伝いをしたり、冷蔵庫から何かを取り出したりする人、年末大売り出しのこと、夏に海水浴に行ったこと、孫ができたことなどを話している人、など、など・・・・。その時、入り口の戸が開きました。みんな、話を止めました。入口に目を向ける人もいました。
ジャケット姿の二人の若者が、手にコートを持って、蕎麦屋に入って来ました。溜息とともに、宴の喧騒がもとに戻りました。女将が、「すみませんが満席なので・・・・。」と二人に丁重にお断りしようとした時、着物姿の婦人が入ってきて二人の間に立ちました。みんな固唾(かたず)をのんで、耳をそばだてました。
「あの・・・かけ蕎麦・・・三つ・・・お願いできますか?」
女将は、その声を聞いてはっとしました。決して忘れられないあの記憶―――十数年前店に来た、母親と二人の息子―――が蘇りました。
女将の視線は、驚きのあまり、目を見開(みひら)いている夫と、今やって来たばかりの三人の間を、行ったり来たりしました。
「あっ・・・えーと・・・そちら・・・そちらさまは・・・」女将はとまどいながら言いました。
若者の一人が答えました。
「私たちは十四年前の大晦日に、ここで一杯のかけ蕎麦を三人で食べた母子(おやこ)です。一杯のかけ蕎麦に勇気づけられ、おかげで、三人で何とか助け合いやって来ました。その後、母の実家の滋賀県に移りましたが、今年、私は医師国家試験に合格し、研修医として京都大学付属病院で働いています。そして来年の4月からは札幌総合病院で勤務することになっています。今回、病院関係者との最初の打ち合わせと、父親の墓前報告を兼ねて札幌に来ました。弟は、蕎麦屋さんにはなりませんでしたが、京都の銀行に勤めております。人生で最高の贅沢・・・大晦日に母と一緒に北海亭に行って、かけ蕎麦を三つ注文する、ということを弟と計画しました。
若者の話を頷(うなづ)きながら聞く店主と女将の目には涙が溢(あふ)れてきました。
入口近くのテーブルで蕎麦を啜(すす)っていた八百屋のおやじさんは、蕎麦をゴクッと飲み込むと、立ち上がりました。
また一年が過ぎました・・・北海亭では、九時半を過ぎると、二番テーブルに「予約席」の札が置かれました。でもあの母親と二人の息子は現れませんでした。次の年も、その次の年も、三人のために二番テーブルを用意しましたが、三人は現れませんでした。
北海亭は改装され、新しいテーブルとイスに入れ替わりましたが、古びた二番テーブルとイスは昔のままに、新しいものに囲まれるように置いてありました。
「何だって、こんなところに古いテーブルとイスが置いてあるんですか?」
と不思議がる客もいました。店主と女将(おかみ)は「一杯のかけ蕎麦」の由来(ゆらい)を語り、この古いテーブルでどんなに励まされたか、三人がいつの日かやって来たら、このテーブルに座ってもらうのだ、と付け加えました。
「幸せのテーブル」の話は口コミで広まっていきました。実際その評判のテーブルで蕎麦を食べようと遠い所からやって来た女子校生や、「幸せのテーブル」が空くのを待って注文し直す若いカップルもいました。
数年が過ぎたある大晦日、家族同様の付き合いの店主の友人たちが仕事を終えて、次から次へと集まって来ました。
彼らにとっては、この数年来続いている年中行事でした。北海亭で、除夜の鐘を聞きながら、年越し蕎麦を食べて、仲間とその家族全員で最寄りの神社に詣でるというものでした。
九時半を過ぎ、刺し身の大皿を持って入って来た魚屋夫婦を皮切りに、三十人以上の友人たちが酒やおつまみを持ってやって来ました。店内は一気に賑(にぎ)やかになりました。
「二番テーブル」のことは誰もが知っていましたが、あの三人が今年も来ていないことは口にしませんでした。「予約席」が空いていても、誰も座らず、テーブルのそばの狭い座敷に、肩を寄せ合って座り、後から来る人のために、スペースを作っておきました。
十時過ぎ、宴はたけなわになりました。飲んだり食べたりする人、店主の料理の手伝いをしたり、冷蔵庫から何かを取り出したりする人、年末大売り出しのこと、夏に海水浴に行ったこと、孫ができたことなどを話している人、など、など・・・・。その時、入り口の戸が開きました。みんな、話を止めました。入口に目を向ける人もいました。
ジャケット姿の二人の若者が、手にコートを持って、蕎麦屋に入って来ました。溜息とともに、宴の喧騒がもとに戻りました。女将が、「すみませんが満席なので・・・・。」と二人に丁重にお断りしようとした時、着物姿の婦人が入ってきて二人の間に立ちました。みんな固唾(かたず)をのんで、耳をそばだてました。
「あの・・・かけ蕎麦・・・三つ・・・お願いできますか?」
女将は、その声を聞いてはっとしました。決して忘れられないあの記憶―――十数年前店に来た、母親と二人の息子―――が蘇りました。
女将の視線は、驚きのあまり、目を見開(みひら)いている夫と、今やって来たばかりの三人の間を、行ったり来たりしました。
「あっ・・・えーと・・・そちら・・・そちらさまは・・・」女将はとまどいながら言いました。
若者の一人が答えました。
「私たちは十四年前の大晦日に、ここで一杯のかけ蕎麦を三人で食べた母子(おやこ)です。一杯のかけ蕎麦に勇気づけられ、おかげで、三人で何とか助け合いやって来ました。その後、母の実家の滋賀県に移りましたが、今年、私は医師国家試験に合格し、研修医として京都大学付属病院で働いています。そして来年の4月からは札幌総合病院で勤務することになっています。今回、病院関係者との最初の打ち合わせと、父親の墓前報告を兼ねて札幌に来ました。弟は、蕎麦屋さんにはなりませんでしたが、京都の銀行に勤めております。人生で最高の贅沢・・・大晦日に母と一緒に北海亭に行って、かけ蕎麦を三つ注文する、ということを弟と計画しました。
若者の話を頷(うなづ)きながら聞く店主と女将の目には涙が溢(あふ)れてきました。
入口近くのテーブルで蕎麦を啜(すす)っていた八百屋のおやじさんは、蕎麦をゴクッと飲み込むと、立ち上がりました。
 「よう、お二人さん!何をもたもたしているんだよ。十年間、大晦日の十時に来る予約席のお客を待っていたんだろ。ついに来たんだよ。お客さんをテーブルに通しなよ!」
女将は、八百屋のおやじさんの肩を叩くと、気を落ち着けて、大きな声で言いました。
「いらっしゃいませ!お待ちしておりました。こちらへどうぞ。二番テーブル、かけ三丁!」
「あいよ、かけ三丁!」
店主は、いつもの無愛想な顔を涙で濡らして答えました。
蕎麦屋では、突如として一斉に拍手と喝采が湧き起こりました。
外では、ちょっと前まで降っていた粉雪も止み、新雪に映える北海亭の暖簾(のれん)が元旦の風に揺れていました。(kudos)
一杯のかけ蕎麦
「よう、お二人さん!何をもたもたしているんだよ。十年間、大晦日の十時に来る予約席のお客を待っていたんだろ。ついに来たんだよ。お客さんをテーブルに通しなよ!」
女将は、八百屋のおやじさんの肩を叩くと、気を落ち着けて、大きな声で言いました。
「いらっしゃいませ!お待ちしておりました。こちらへどうぞ。二番テーブル、かけ三丁!」
「あいよ、かけ三丁!」
店主は、いつもの無愛想な顔を涙で濡らして答えました。
蕎麦屋では、突如として一斉に拍手と喝采が湧き起こりました。
外では、ちょっと前まで降っていた粉雪も止み、新雪に映える北海亭の暖簾(のれん)が元旦の風に揺れていました。(kudos)
一杯のかけ蕎麦
