
水戸黄門
ご存知「水戸黄門」は皆さんがお気に入りの話だと思います。水戸黄門は歴史上実在の人物です。江戸時代末期、彼の逸話は講談師によって語られ始め、その話は庶民の間に広まっていきました。本名は水戸光圀(1628-1700)。水戸(茨城県)藩主、身分は中納言(別名、黄門)であったため、水戸黄門とも呼ばれました。六十三歳で藩主の座を甥にゆずりました。名君と言われ、さらには日本史の研究、「大日本史」の編纂にもとりかかりました。また大の旅好きでもありました。
水戸黄門は1969年、テレビの連続人気番組として登場して以来、千回以上続いております。その壱話をお話ししたいと思います。
まずは黄門さまの個性あふれる一行を紹介しましょう。
助さん―佐々木助三郎、水戸藩士、剣の達人。
格さん―渥美格之進、水戸藩士、柔の達人。
八兵衛―町人、黄門さまの世話係。
お銀―忍びの女人。美貌の町娘。
飛猿―忍びの者。旅のくすり売り。
弥吉―忍びの者。妻とそば屋の商い。
 ある日のこと、黄門さまの一行は、道中、天気にも恵まれ、、たわいないことを話しながら歩いていました。ある街にさしかかった時のことです。倒れそうにふらふらとこちらに向かってくる男とばったり出会いました。傷を負っていると見え、肩から血が流れていました。黄門さまは飛猿に言いました。
「飛猿。血を流しておる。手当てしてあげなさい。」
飛猿は、手ぬぐいを引き裂くと、男の肩に包帯をしました。
「どうしたんですか。いったい誰に切られたのですか。」黄門さまは男に尋ねました。
「手、手前は米問屋、大、大黒屋で働いているものですが、たまたま秘密を知ってしまいました。や、やつらが突然切りつけて来ました。」男の声はだんだんと弱くなると、息を引き取ってしまいました。
「何か容易でないことが起こっているようです。皆さん、この男が働いていた所を調べて、何が起こっているのか探って下さい。何か手を打たなくてはなりません。急ぎましょう。」と黄門さまは言いました。
大黒屋は町一番の米問屋、すぐにわかりました。お銀は店の天井裏に身を隠し、飛猿は主人の行動を数日探りました。二人は、主人の所に誰が来るか、または主人が誰に会いに行くか、辛抱強く待ちました。すると主人が代官に会うために料亭に出かけるという知らせを入手しました。お銀は、そこの女中になりすましました。酒を注ぎ、二人をくつろがせました。酒が入ると、二人の警戒心は消え、襖を通して、二人の話が、お銀の耳に入ってきました。
「誰にも気づかれなかっただろうな。」
「心配ございません。そんなへまはやりません。」
「例のものは持ってきたろうな。大黒屋。」
「もちろんでございます。これにございます。」大黒屋は持参した風呂敷をほどき、中の木箱を見せました。
「よし。中を見せろ。」大黒屋は金貨百枚が入った箱を開けました。
「見事じゃ。この黄金の色。ご苦労。」
さて、一方、弥吉は米問屋の蔵に忍び込み、予想を越えた米俵が積まれているのを見つけました。
助さん、格さんは、お百姓さんが、ひどく苦しめられ、年貢の他にも米を出さねばならないことを耳にしました。
黄門さまは、お銀、弥吉、助さん、格さんからこれまでのことを聞きました。
「ご苦労さんでした。よくわかりました。かわいそうな民を助けてあげましょう。代官と大黒屋を懲らしめてあげましょう。」
黄門さまは、助さん、格さんを伴って藩主のところに出かけて行くと、余分な取立てを止めるように言います。しかし、藩主は不審げにこう言い返します。
「どちら様でしょう。ご老人。何のことをお話でしょう。おっしゃるような取り立ては誓って行っておりません。いつも頭にあるのは民のことです。そこまでおっしゃるのでしたら、証拠を見せて下さい。」
すると、突然、代官が大声で、
「皆のもの。殿を亡き者にせんとするならず者だ。みなの者、出会え。切れ、切り捨てえ。」
刀を持った侍たちが黄門さまと二人を取り囲みます。黄門さまは、こう言います。
「仕方ないでしょう。助さん、格さん、懲らしめてやりなさい。」
飛猿、お銀、弥吉も修羅場に加わり黄門さまの手助け。相手は大勢の侍、一方はたったの六人、勝負はあったかに思えましたが、ご存知のとおり、われらが黄門さま一行。黄門さま直々、杖で相手をやっつける。助さんは剣の達人ではあるが決して相手は切りません。相手を峰打ちするだけです。それでも大勢の相手を負かしてしまいます。格さんは柔の達人、二本の腕と手だけで戦いますが、格さんを打ち負かせるものはいません。
しばらくして、黄門さまは声を大きくして言います。
「助さん、格さん、もうよいでしょう。」
すると、助さんが叫びます。
「刀を納めい、皆の者。」そして右手で印籠を胸元から取り出すと、高らかに掲げ、続けます。
「この紋所が目に入らぬか。ここにおわす御方をどなたと心得る。」
一同、印籠を見上げます。そこにはあの徳川三つ葉葵のご紋所が。
格さんがその後を続けて、
「こちらにおわすは、先の副将軍水戸光圀公であらせられるぞ。頭が高い。控えおろう。」
藩主は勿論、誰もが驚き、戸惑い、黄門さまと一行の前にひざまづく。
ころを見計らい八兵衛が大黒屋を引き連れ登場。
「この男が全部白状しましたぜ。私腹をこやさがんがため、代官と大黒屋で悪事を企んだとのことです。」
黄門さまは代官を責め立てる。
「そちの役割は藩主を支えること。しかし、そちは自らの私欲のみを考え、大黒屋と謀って悪事を企て、私腹をこやした。重い取立てを課せられた農民の苦しみを思えば、言い訳無用じゃ。厳しく罰せられることを覚悟するのじゃな。」
黄門さまは米問屋に向かって、
「大黒屋、そちは米の商いを不当に行った。代官に賄賂を送り、それ相当の見返りをもらい私腹を肥やしたことは明白である。今後米を商うことはいっさいならん。即刻、所払いになるであろう。」
藩主は、恐れおののきながらも、我に返り、家来に命じる。
「このものどもを牢屋に連れて行け。後ほど直々に取り調べるであろう。」
ある日のこと、黄門さまの一行は、道中、天気にも恵まれ、、たわいないことを話しながら歩いていました。ある街にさしかかった時のことです。倒れそうにふらふらとこちらに向かってくる男とばったり出会いました。傷を負っていると見え、肩から血が流れていました。黄門さまは飛猿に言いました。
「飛猿。血を流しておる。手当てしてあげなさい。」
飛猿は、手ぬぐいを引き裂くと、男の肩に包帯をしました。
「どうしたんですか。いったい誰に切られたのですか。」黄門さまは男に尋ねました。
「手、手前は米問屋、大、大黒屋で働いているものですが、たまたま秘密を知ってしまいました。や、やつらが突然切りつけて来ました。」男の声はだんだんと弱くなると、息を引き取ってしまいました。
「何か容易でないことが起こっているようです。皆さん、この男が働いていた所を調べて、何が起こっているのか探って下さい。何か手を打たなくてはなりません。急ぎましょう。」と黄門さまは言いました。
大黒屋は町一番の米問屋、すぐにわかりました。お銀は店の天井裏に身を隠し、飛猿は主人の行動を数日探りました。二人は、主人の所に誰が来るか、または主人が誰に会いに行くか、辛抱強く待ちました。すると主人が代官に会うために料亭に出かけるという知らせを入手しました。お銀は、そこの女中になりすましました。酒を注ぎ、二人をくつろがせました。酒が入ると、二人の警戒心は消え、襖を通して、二人の話が、お銀の耳に入ってきました。
「誰にも気づかれなかっただろうな。」
「心配ございません。そんなへまはやりません。」
「例のものは持ってきたろうな。大黒屋。」
「もちろんでございます。これにございます。」大黒屋は持参した風呂敷をほどき、中の木箱を見せました。
「よし。中を見せろ。」大黒屋は金貨百枚が入った箱を開けました。
「見事じゃ。この黄金の色。ご苦労。」
さて、一方、弥吉は米問屋の蔵に忍び込み、予想を越えた米俵が積まれているのを見つけました。
助さん、格さんは、お百姓さんが、ひどく苦しめられ、年貢の他にも米を出さねばならないことを耳にしました。
黄門さまは、お銀、弥吉、助さん、格さんからこれまでのことを聞きました。
「ご苦労さんでした。よくわかりました。かわいそうな民を助けてあげましょう。代官と大黒屋を懲らしめてあげましょう。」
黄門さまは、助さん、格さんを伴って藩主のところに出かけて行くと、余分な取立てを止めるように言います。しかし、藩主は不審げにこう言い返します。
「どちら様でしょう。ご老人。何のことをお話でしょう。おっしゃるような取り立ては誓って行っておりません。いつも頭にあるのは民のことです。そこまでおっしゃるのでしたら、証拠を見せて下さい。」
すると、突然、代官が大声で、
「皆のもの。殿を亡き者にせんとするならず者だ。みなの者、出会え。切れ、切り捨てえ。」
刀を持った侍たちが黄門さまと二人を取り囲みます。黄門さまは、こう言います。
「仕方ないでしょう。助さん、格さん、懲らしめてやりなさい。」
飛猿、お銀、弥吉も修羅場に加わり黄門さまの手助け。相手は大勢の侍、一方はたったの六人、勝負はあったかに思えましたが、ご存知のとおり、われらが黄門さま一行。黄門さま直々、杖で相手をやっつける。助さんは剣の達人ではあるが決して相手は切りません。相手を峰打ちするだけです。それでも大勢の相手を負かしてしまいます。格さんは柔の達人、二本の腕と手だけで戦いますが、格さんを打ち負かせるものはいません。
しばらくして、黄門さまは声を大きくして言います。
「助さん、格さん、もうよいでしょう。」
すると、助さんが叫びます。
「刀を納めい、皆の者。」そして右手で印籠を胸元から取り出すと、高らかに掲げ、続けます。
「この紋所が目に入らぬか。ここにおわす御方をどなたと心得る。」
一同、印籠を見上げます。そこにはあの徳川三つ葉葵のご紋所が。
格さんがその後を続けて、
「こちらにおわすは、先の副将軍水戸光圀公であらせられるぞ。頭が高い。控えおろう。」
藩主は勿論、誰もが驚き、戸惑い、黄門さまと一行の前にひざまづく。
ころを見計らい八兵衛が大黒屋を引き連れ登場。
「この男が全部白状しましたぜ。私腹をこやさがんがため、代官と大黒屋で悪事を企んだとのことです。」
黄門さまは代官を責め立てる。
「そちの役割は藩主を支えること。しかし、そちは自らの私欲のみを考え、大黒屋と謀って悪事を企て、私腹をこやした。重い取立てを課せられた農民の苦しみを思えば、言い訳無用じゃ。厳しく罰せられることを覚悟するのじゃな。」
黄門さまは米問屋に向かって、
「大黒屋、そちは米の商いを不当に行った。代官に賄賂を送り、それ相当の見返りをもらい私腹を肥やしたことは明白である。今後米を商うことはいっさいならん。即刻、所払いになるであろう。」
藩主は、恐れおののきながらも、我に返り、家来に命じる。
「このものどもを牢屋に連れて行け。後ほど直々に取り調べるであろう。」
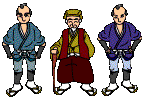 そして、黄門さまに、
「このような失態をお見せいたしまして誠に申し訳ございません。私が迂闊でありました。私の手落ち、この件の責任は全て私にございます。どうかお許しください。今後は二度とこのような事のないように注意いたします。」
「噂によれば、いいご子息をお持ちだとか。隠居して、ご子息にお家を継がせたが良かろう。以上。」さらに続けます。
「しかし、そうじゃな、ご子息にはまだ手助けが必要でしょうな。名君になるよう助言してあげるのですな。」
次の朝、黄門さまたちの旅はまた始まります。一件落着し、黄門さま一行の顔は輝いていました。黄門さまも機嫌よく、言いました。
「さあ、出かけましょうか。」そして大声で笑いました。
「は、は、は。」(2004.3.1)
そして、黄門さまに、
「このような失態をお見せいたしまして誠に申し訳ございません。私が迂闊でありました。私の手落ち、この件の責任は全て私にございます。どうかお許しください。今後は二度とこのような事のないように注意いたします。」
「噂によれば、いいご子息をお持ちだとか。隠居して、ご子息にお家を継がせたが良かろう。以上。」さらに続けます。
「しかし、そうじゃな、ご子息にはまだ手助けが必要でしょうな。名君になるよう助言してあげるのですな。」
次の朝、黄門さまたちの旅はまた始まります。一件落着し、黄門さま一行の顔は輝いていました。黄門さまも機嫌よく、言いました。
「さあ、出かけましょうか。」そして大声で笑いました。
「は、は、は。」(2004.3.1)



 ある日のこと、黄門さまの一行は、道中、天気にも恵まれ、、たわいないことを話しながら歩いていました。ある街にさしかかった時のことです。倒れそうにふらふらとこちらに向かってくる男とばったり出会いました。傷を負っていると見え、肩から血が流れていました。黄門さまは飛猿に言いました。
「飛猿。血を流しておる。手当てしてあげなさい。」
飛猿は、手ぬぐいを引き裂くと、男の肩に包帯をしました。
「どうしたんですか。いったい誰に切られたのですか。」黄門さまは男に尋ねました。
「手、手前は米問屋、大、大黒屋で働いているものですが、たまたま秘密を知ってしまいました。や、やつらが突然切りつけて来ました。」男の声はだんだんと弱くなると、息を引き取ってしまいました。
「何か容易でないことが起こっているようです。皆さん、この男が働いていた所を調べて、何が起こっているのか探って下さい。何か手を打たなくてはなりません。急ぎましょう。」と黄門さまは言いました。
大黒屋は町一番の米問屋、すぐにわかりました。お銀は店の天井裏に身を隠し、飛猿は主人の行動を数日探りました。二人は、主人の所に誰が来るか、または主人が誰に会いに行くか、辛抱強く待ちました。すると主人が代官に会うために料亭に出かけるという知らせを入手しました。お銀は、そこの女中になりすましました。酒を注ぎ、二人をくつろがせました。酒が入ると、二人の警戒心は消え、襖を通して、二人の話が、お銀の耳に入ってきました。
「誰にも気づかれなかっただろうな。」
「心配ございません。そんなへまはやりません。」
「例のものは持ってきたろうな。大黒屋。」
「もちろんでございます。これにございます。」大黒屋は持参した風呂敷をほどき、中の木箱を見せました。
「よし。中を見せろ。」大黒屋は金貨百枚が入った箱を開けました。
「見事じゃ。この黄金の色。ご苦労。」
さて、一方、弥吉は米問屋の蔵に忍び込み、予想を越えた米俵が積まれているのを見つけました。
助さん、格さんは、お百姓さんが、ひどく苦しめられ、年貢の他にも米を出さねばならないことを耳にしました。
黄門さまは、お銀、弥吉、助さん、格さんからこれまでのことを聞きました。
「ご苦労さんでした。よくわかりました。かわいそうな民を助けてあげましょう。代官と大黒屋を懲らしめてあげましょう。」
黄門さまは、助さん、格さんを伴って藩主のところに出かけて行くと、余分な取立てを止めるように言います。しかし、藩主は不審げにこう言い返します。
「どちら様でしょう。ご老人。何のことをお話でしょう。おっしゃるような取り立ては誓って行っておりません。いつも頭にあるのは民のことです。そこまでおっしゃるのでしたら、証拠を見せて下さい。」
すると、突然、代官が大声で、
「皆のもの。殿を亡き者にせんとするならず者だ。みなの者、出会え。切れ、切り捨てえ。」
刀を持った侍たちが黄門さまと二人を取り囲みます。黄門さまは、こう言います。
「仕方ないでしょう。助さん、格さん、懲らしめてやりなさい。」
飛猿、お銀、弥吉も修羅場に加わり黄門さまの手助け。相手は大勢の侍、一方はたったの六人、勝負はあったかに思えましたが、ご存知のとおり、われらが黄門さま一行。黄門さま直々、杖で相手をやっつける。助さんは剣の達人ではあるが決して相手は切りません。相手を峰打ちするだけです。それでも大勢の相手を負かしてしまいます。格さんは柔の達人、二本の腕と手だけで戦いますが、格さんを打ち負かせるものはいません。
しばらくして、黄門さまは声を大きくして言います。
「助さん、格さん、もうよいでしょう。」
すると、助さんが叫びます。
「刀を納めい、皆の者。」そして右手で印籠を胸元から取り出すと、高らかに掲げ、続けます。
「この紋所が目に入らぬか。ここにおわす御方をどなたと心得る。」
一同、印籠を見上げます。そこにはあの徳川三つ葉葵のご紋所が。
格さんがその後を続けて、
「こちらにおわすは、先の副将軍水戸光圀公であらせられるぞ。頭が高い。控えおろう。」
藩主は勿論、誰もが驚き、戸惑い、黄門さまと一行の前にひざまづく。
ころを見計らい八兵衛が大黒屋を引き連れ登場。
「この男が全部白状しましたぜ。私腹をこやさがんがため、代官と大黒屋で悪事を企んだとのことです。」
黄門さまは代官を責め立てる。
「そちの役割は藩主を支えること。しかし、そちは自らの私欲のみを考え、大黒屋と謀って悪事を企て、私腹をこやした。重い取立てを課せられた農民の苦しみを思えば、言い訳無用じゃ。厳しく罰せられることを覚悟するのじゃな。」
黄門さまは米問屋に向かって、
「大黒屋、そちは米の商いを不当に行った。代官に賄賂を送り、それ相当の見返りをもらい私腹を肥やしたことは明白である。今後米を商うことはいっさいならん。即刻、所払いになるであろう。」
藩主は、恐れおののきながらも、我に返り、家来に命じる。
「このものどもを牢屋に連れて行け。後ほど直々に取り調べるであろう。」
ある日のこと、黄門さまの一行は、道中、天気にも恵まれ、、たわいないことを話しながら歩いていました。ある街にさしかかった時のことです。倒れそうにふらふらとこちらに向かってくる男とばったり出会いました。傷を負っていると見え、肩から血が流れていました。黄門さまは飛猿に言いました。
「飛猿。血を流しておる。手当てしてあげなさい。」
飛猿は、手ぬぐいを引き裂くと、男の肩に包帯をしました。
「どうしたんですか。いったい誰に切られたのですか。」黄門さまは男に尋ねました。
「手、手前は米問屋、大、大黒屋で働いているものですが、たまたま秘密を知ってしまいました。や、やつらが突然切りつけて来ました。」男の声はだんだんと弱くなると、息を引き取ってしまいました。
「何か容易でないことが起こっているようです。皆さん、この男が働いていた所を調べて、何が起こっているのか探って下さい。何か手を打たなくてはなりません。急ぎましょう。」と黄門さまは言いました。
大黒屋は町一番の米問屋、すぐにわかりました。お銀は店の天井裏に身を隠し、飛猿は主人の行動を数日探りました。二人は、主人の所に誰が来るか、または主人が誰に会いに行くか、辛抱強く待ちました。すると主人が代官に会うために料亭に出かけるという知らせを入手しました。お銀は、そこの女中になりすましました。酒を注ぎ、二人をくつろがせました。酒が入ると、二人の警戒心は消え、襖を通して、二人の話が、お銀の耳に入ってきました。
「誰にも気づかれなかっただろうな。」
「心配ございません。そんなへまはやりません。」
「例のものは持ってきたろうな。大黒屋。」
「もちろんでございます。これにございます。」大黒屋は持参した風呂敷をほどき、中の木箱を見せました。
「よし。中を見せろ。」大黒屋は金貨百枚が入った箱を開けました。
「見事じゃ。この黄金の色。ご苦労。」
さて、一方、弥吉は米問屋の蔵に忍び込み、予想を越えた米俵が積まれているのを見つけました。
助さん、格さんは、お百姓さんが、ひどく苦しめられ、年貢の他にも米を出さねばならないことを耳にしました。
黄門さまは、お銀、弥吉、助さん、格さんからこれまでのことを聞きました。
「ご苦労さんでした。よくわかりました。かわいそうな民を助けてあげましょう。代官と大黒屋を懲らしめてあげましょう。」
黄門さまは、助さん、格さんを伴って藩主のところに出かけて行くと、余分な取立てを止めるように言います。しかし、藩主は不審げにこう言い返します。
「どちら様でしょう。ご老人。何のことをお話でしょう。おっしゃるような取り立ては誓って行っておりません。いつも頭にあるのは民のことです。そこまでおっしゃるのでしたら、証拠を見せて下さい。」
すると、突然、代官が大声で、
「皆のもの。殿を亡き者にせんとするならず者だ。みなの者、出会え。切れ、切り捨てえ。」
刀を持った侍たちが黄門さまと二人を取り囲みます。黄門さまは、こう言います。
「仕方ないでしょう。助さん、格さん、懲らしめてやりなさい。」
飛猿、お銀、弥吉も修羅場に加わり黄門さまの手助け。相手は大勢の侍、一方はたったの六人、勝負はあったかに思えましたが、ご存知のとおり、われらが黄門さま一行。黄門さま直々、杖で相手をやっつける。助さんは剣の達人ではあるが決して相手は切りません。相手を峰打ちするだけです。それでも大勢の相手を負かしてしまいます。格さんは柔の達人、二本の腕と手だけで戦いますが、格さんを打ち負かせるものはいません。
しばらくして、黄門さまは声を大きくして言います。
「助さん、格さん、もうよいでしょう。」
すると、助さんが叫びます。
「刀を納めい、皆の者。」そして右手で印籠を胸元から取り出すと、高らかに掲げ、続けます。
「この紋所が目に入らぬか。ここにおわす御方をどなたと心得る。」
一同、印籠を見上げます。そこにはあの徳川三つ葉葵のご紋所が。
格さんがその後を続けて、
「こちらにおわすは、先の副将軍水戸光圀公であらせられるぞ。頭が高い。控えおろう。」
藩主は勿論、誰もが驚き、戸惑い、黄門さまと一行の前にひざまづく。
ころを見計らい八兵衛が大黒屋を引き連れ登場。
「この男が全部白状しましたぜ。私腹をこやさがんがため、代官と大黒屋で悪事を企んだとのことです。」
黄門さまは代官を責め立てる。
「そちの役割は藩主を支えること。しかし、そちは自らの私欲のみを考え、大黒屋と謀って悪事を企て、私腹をこやした。重い取立てを課せられた農民の苦しみを思えば、言い訳無用じゃ。厳しく罰せられることを覚悟するのじゃな。」
黄門さまは米問屋に向かって、
「大黒屋、そちは米の商いを不当に行った。代官に賄賂を送り、それ相当の見返りをもらい私腹を肥やしたことは明白である。今後米を商うことはいっさいならん。即刻、所払いになるであろう。」
藩主は、恐れおののきながらも、我に返り、家来に命じる。
「このものどもを牢屋に連れて行け。後ほど直々に取り調べるであろう。」
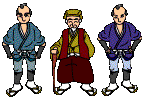 そして、黄門さまに、
「このような失態をお見せいたしまして誠に申し訳ございません。私が迂闊でありました。私の手落ち、この件の責任は全て私にございます。どうかお許しください。今後は二度とこのような事のないように注意いたします。」
「噂によれば、いいご子息をお持ちだとか。隠居して、ご子息にお家を継がせたが良かろう。以上。」さらに続けます。
「しかし、そうじゃな、ご子息にはまだ手助けが必要でしょうな。名君になるよう助言してあげるのですな。」
次の朝、黄門さまたちの旅はまた始まります。一件落着し、黄門さま一行の顔は輝いていました。黄門さまも機嫌よく、言いました。
「さあ、出かけましょうか。」そして大声で笑いました。
「は、は、は。」(2004.3.1)
そして、黄門さまに、
「このような失態をお見せいたしまして誠に申し訳ございません。私が迂闊でありました。私の手落ち、この件の責任は全て私にございます。どうかお許しください。今後は二度とこのような事のないように注意いたします。」
「噂によれば、いいご子息をお持ちだとか。隠居して、ご子息にお家を継がせたが良かろう。以上。」さらに続けます。
「しかし、そうじゃな、ご子息にはまだ手助けが必要でしょうな。名君になるよう助言してあげるのですな。」
次の朝、黄門さまたちの旅はまた始まります。一件落着し、黄門さま一行の顔は輝いていました。黄門さまも機嫌よく、言いました。
「さあ、出かけましょうか。」そして大声で笑いました。
「は、は、は。」(2004.3.1)
