
身投げ僧
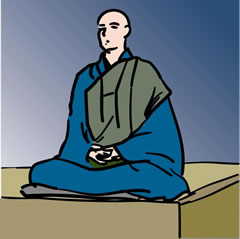 むかし、むかし、都のはずれに一人の僧が住んでいました。その僧は日々の勤行(ごんぎょう)として仏の教えを説いておりました。
ある日、僧は、寺へ説法を聞きに来る人の数が減ってきていることに気づき、何とかしなければと思いました。
そこで、ある日、説法の終わりにこんなことを言いました。
「近い内に、私は川に身を投げて、この世に別れを告げようと思っています。」
皆は驚き、そのわけを尋ねました。
僧は、こう答えました。
「今まで悪事を働いてきた人々のことが気がかりなのです。その人達の魂が、死んで後地獄に堕ちるのを、何とか救いたいのです。」
次に、皆はいつそうするつもりなのですか、と尋ねました。僧は、しばし考え、こう言いました。
「入水(じゅすい)する前にすることがあります。この寺で百日間読経(どきょう)して私の身を清めなければなりません。」
そのうわさはこんなふうに都中に広まりました。
「あの寺のお坊さんが、私たちを救うために川に身を投げられるそうだ。」
「きっと高僧に違いない。今の内にお坊さんの所に行ってわれわれの幸せを祈った方がいいぞ。」
寺を訪れる人の数がどんどん増えていきました。参道は説法を聞こうとする人々であふれかえりました。僧は、それを見て至極満足でしたが、ふとした思いつきで宣言してしまった入水のことが段々と気にかかってきました。
履行(りこう)の日が近づいて来ましたが、平静を装っていました。毎日、参拝者の前にもの静かに座して、目を半眼に開いて読経しました。その目をかっと見開くたびに聴衆に顔を向けました。
「ほら!目を大きく開けたぞ。何と気高いお姿だ!」顔を見た人は囁き合いました。夕方、僧は静かに立ち上がると、庫裏(くり)の方へ消えていきました。
百日間の勤行が終わり、とうとうその日がやって来ました。物好きな見物人がすでに川岸に集まっていました。僧が岸に到着すると一斉に歓声があがりました。僧を小舟にのせた船頭は、川の中程まで漕ぐと、舟をそこで止めました。
「この身を捧げるにはいささか明るすぎる。日の入りまで待つことにしよう。」
僧は船頭に言うと、しばし川に視線を下ろしました。」
僧は、相変わらず舟の中から川面(かわも)を眺め続け、身動き一つしませんでした。僧の入水を見ようと川岸に集まった人々ですが、待ちくたびれて嫌気がさしてきました。中には我慢できない人もいて、一人、また一人と立ち去り始めました。それでも、まだ沢山の人が残っており、野次を飛ばし始めました。
「この目であの坊さんの末期(まつご)を見届けたいものだ。あとどれ位待たせる気だ。」
「身投げすると明言しておきながら、どうしてこんなに時間がかかるんだ。」
「どうも死にたくなさそうだ。」
そうこうしているうちに、日もすっかり暮れました。僧は舟の中で立ち上がりました。
「いよいよだぞ、お坊さんが川に飛び込むぞ!」みんな大声を上げて、手を叩きました。
むかし、むかし、都のはずれに一人の僧が住んでいました。その僧は日々の勤行(ごんぎょう)として仏の教えを説いておりました。
ある日、僧は、寺へ説法を聞きに来る人の数が減ってきていることに気づき、何とかしなければと思いました。
そこで、ある日、説法の終わりにこんなことを言いました。
「近い内に、私は川に身を投げて、この世に別れを告げようと思っています。」
皆は驚き、そのわけを尋ねました。
僧は、こう答えました。
「今まで悪事を働いてきた人々のことが気がかりなのです。その人達の魂が、死んで後地獄に堕ちるのを、何とか救いたいのです。」
次に、皆はいつそうするつもりなのですか、と尋ねました。僧は、しばし考え、こう言いました。
「入水(じゅすい)する前にすることがあります。この寺で百日間読経(どきょう)して私の身を清めなければなりません。」
そのうわさはこんなふうに都中に広まりました。
「あの寺のお坊さんが、私たちを救うために川に身を投げられるそうだ。」
「きっと高僧に違いない。今の内にお坊さんの所に行ってわれわれの幸せを祈った方がいいぞ。」
寺を訪れる人の数がどんどん増えていきました。参道は説法を聞こうとする人々であふれかえりました。僧は、それを見て至極満足でしたが、ふとした思いつきで宣言してしまった入水のことが段々と気にかかってきました。
履行(りこう)の日が近づいて来ましたが、平静を装っていました。毎日、参拝者の前にもの静かに座して、目を半眼に開いて読経しました。その目をかっと見開くたびに聴衆に顔を向けました。
「ほら!目を大きく開けたぞ。何と気高いお姿だ!」顔を見た人は囁き合いました。夕方、僧は静かに立ち上がると、庫裏(くり)の方へ消えていきました。
百日間の勤行が終わり、とうとうその日がやって来ました。物好きな見物人がすでに川岸に集まっていました。僧が岸に到着すると一斉に歓声があがりました。僧を小舟にのせた船頭は、川の中程まで漕ぐと、舟をそこで止めました。
「この身を捧げるにはいささか明るすぎる。日の入りまで待つことにしよう。」
僧は船頭に言うと、しばし川に視線を下ろしました。」
僧は、相変わらず舟の中から川面(かわも)を眺め続け、身動き一つしませんでした。僧の入水を見ようと川岸に集まった人々ですが、待ちくたびれて嫌気がさしてきました。中には我慢できない人もいて、一人、また一人と立ち去り始めました。それでも、まだ沢山の人が残っており、野次を飛ばし始めました。
「この目であの坊さんの末期(まつご)を見届けたいものだ。あとどれ位待たせる気だ。」
「身投げすると明言しておきながら、どうしてこんなに時間がかかるんだ。」
「どうも死にたくなさそうだ。」
そうこうしているうちに、日もすっかり暮れました。僧は舟の中で立ち上がりました。
「いよいよだぞ、お坊さんが川に飛び込むぞ!」みんな大声を上げて、手を叩きました。
 僧は、衣(ころも)を脱いで褌(ふんどし)一丁になると、合掌したまま足から川に飛び込みました。
僧の身体は一度は水の中に沈みましたが、浮かび上がり、また沈み、それからぷかっと浮かび上がりました。そして川岸に向かって手足をばたつかせ始めました。
「どうやらこの坊さんは、自分で言ったことを今は後悔しているんだ。この世にまだ未練があるようだ。」
一人が、そう言って、僧の両手を掴み、岸に引き揚げてやりました。
僧は、両手を合わせて、その人に言いました。
「命を救っていただき有り難うございました。ご恩は決して忘れません。このお返しはあの世で必ずいたします。」
人々は愛想をつかし、お坊さんの悪口を言い始めました。
「何ってくそ坊主!」
「最初から身投げしようなんて気はなかったのだろう。」
「まんまと騙された。」
中には小石を拾うと僧に向かって投げつける者もいました。
「あいた!痛たた!」
まっ裸のままの僧侶は、頭を自分の手でかばいながら逃げていきました。(Kudos) 原作「宇治拾遺物語」より
僧は、衣(ころも)を脱いで褌(ふんどし)一丁になると、合掌したまま足から川に飛び込みました。
僧の身体は一度は水の中に沈みましたが、浮かび上がり、また沈み、それからぷかっと浮かび上がりました。そして川岸に向かって手足をばたつかせ始めました。
「どうやらこの坊さんは、自分で言ったことを今は後悔しているんだ。この世にまだ未練があるようだ。」
一人が、そう言って、僧の両手を掴み、岸に引き揚げてやりました。
僧は、両手を合わせて、その人に言いました。
「命を救っていただき有り難うございました。ご恩は決して忘れません。このお返しはあの世で必ずいたします。」
人々は愛想をつかし、お坊さんの悪口を言い始めました。
「何ってくそ坊主!」
「最初から身投げしようなんて気はなかったのだろう。」
「まんまと騙された。」
中には小石を拾うと僧に向かって投げつける者もいました。
「あいた!痛たた!」
まっ裸のままの僧侶は、頭を自分の手でかばいながら逃げていきました。(Kudos) 原作「宇治拾遺物語」より



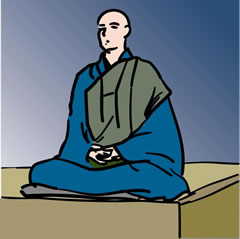 むかし、むかし、都のはずれに一人の僧が住んでいました。その僧は日々の勤行(ごんぎょう)として仏の教えを説いておりました。
ある日、僧は、寺へ説法を聞きに来る人の数が減ってきていることに気づき、何とかしなければと思いました。
そこで、ある日、説法の終わりにこんなことを言いました。
「近い内に、私は川に身を投げて、この世に別れを告げようと思っています。」
皆は驚き、そのわけを尋ねました。
僧は、こう答えました。
「今まで悪事を働いてきた人々のことが気がかりなのです。その人達の魂が、死んで後地獄に堕ちるのを、何とか救いたいのです。」
次に、皆はいつそうするつもりなのですか、と尋ねました。僧は、しばし考え、こう言いました。
「入水(じゅすい)する前にすることがあります。この寺で百日間読経(どきょう)して私の身を清めなければなりません。」
そのうわさはこんなふうに都中に広まりました。
「あの寺のお坊さんが、私たちを救うために川に身を投げられるそうだ。」
「きっと高僧に違いない。今の内にお坊さんの所に行ってわれわれの幸せを祈った方がいいぞ。」
寺を訪れる人の数がどんどん増えていきました。参道は説法を聞こうとする人々であふれかえりました。僧は、それを見て至極満足でしたが、ふとした思いつきで宣言してしまった入水のことが段々と気にかかってきました。
履行(りこう)の日が近づいて来ましたが、平静を装っていました。毎日、参拝者の前にもの静かに座して、目を半眼に開いて読経しました。その目をかっと見開くたびに聴衆に顔を向けました。
「ほら!目を大きく開けたぞ。何と気高いお姿だ!」顔を見た人は囁き合いました。夕方、僧は静かに立ち上がると、庫裏(くり)の方へ消えていきました。
百日間の勤行が終わり、とうとうその日がやって来ました。物好きな見物人がすでに川岸に集まっていました。僧が岸に到着すると一斉に歓声があがりました。僧を小舟にのせた船頭は、川の中程まで漕ぐと、舟をそこで止めました。
「この身を捧げるにはいささか明るすぎる。日の入りまで待つことにしよう。」
僧は船頭に言うと、しばし川に視線を下ろしました。」
僧は、相変わらず舟の中から川面(かわも)を眺め続け、身動き一つしませんでした。僧の入水を見ようと川岸に集まった人々ですが、待ちくたびれて嫌気がさしてきました。中には我慢できない人もいて、一人、また一人と立ち去り始めました。それでも、まだ沢山の人が残っており、野次を飛ばし始めました。
「この目であの坊さんの末期(まつご)を見届けたいものだ。あとどれ位待たせる気だ。」
「身投げすると明言しておきながら、どうしてこんなに時間がかかるんだ。」
「どうも死にたくなさそうだ。」
そうこうしているうちに、日もすっかり暮れました。僧は舟の中で立ち上がりました。
「いよいよだぞ、お坊さんが川に飛び込むぞ!」みんな大声を上げて、手を叩きました。
むかし、むかし、都のはずれに一人の僧が住んでいました。その僧は日々の勤行(ごんぎょう)として仏の教えを説いておりました。
ある日、僧は、寺へ説法を聞きに来る人の数が減ってきていることに気づき、何とかしなければと思いました。
そこで、ある日、説法の終わりにこんなことを言いました。
「近い内に、私は川に身を投げて、この世に別れを告げようと思っています。」
皆は驚き、そのわけを尋ねました。
僧は、こう答えました。
「今まで悪事を働いてきた人々のことが気がかりなのです。その人達の魂が、死んで後地獄に堕ちるのを、何とか救いたいのです。」
次に、皆はいつそうするつもりなのですか、と尋ねました。僧は、しばし考え、こう言いました。
「入水(じゅすい)する前にすることがあります。この寺で百日間読経(どきょう)して私の身を清めなければなりません。」
そのうわさはこんなふうに都中に広まりました。
「あの寺のお坊さんが、私たちを救うために川に身を投げられるそうだ。」
「きっと高僧に違いない。今の内にお坊さんの所に行ってわれわれの幸せを祈った方がいいぞ。」
寺を訪れる人の数がどんどん増えていきました。参道は説法を聞こうとする人々であふれかえりました。僧は、それを見て至極満足でしたが、ふとした思いつきで宣言してしまった入水のことが段々と気にかかってきました。
履行(りこう)の日が近づいて来ましたが、平静を装っていました。毎日、参拝者の前にもの静かに座して、目を半眼に開いて読経しました。その目をかっと見開くたびに聴衆に顔を向けました。
「ほら!目を大きく開けたぞ。何と気高いお姿だ!」顔を見た人は囁き合いました。夕方、僧は静かに立ち上がると、庫裏(くり)の方へ消えていきました。
百日間の勤行が終わり、とうとうその日がやって来ました。物好きな見物人がすでに川岸に集まっていました。僧が岸に到着すると一斉に歓声があがりました。僧を小舟にのせた船頭は、川の中程まで漕ぐと、舟をそこで止めました。
「この身を捧げるにはいささか明るすぎる。日の入りまで待つことにしよう。」
僧は船頭に言うと、しばし川に視線を下ろしました。」
僧は、相変わらず舟の中から川面(かわも)を眺め続け、身動き一つしませんでした。僧の入水を見ようと川岸に集まった人々ですが、待ちくたびれて嫌気がさしてきました。中には我慢できない人もいて、一人、また一人と立ち去り始めました。それでも、まだ沢山の人が残っており、野次を飛ばし始めました。
「この目であの坊さんの末期(まつご)を見届けたいものだ。あとどれ位待たせる気だ。」
「身投げすると明言しておきながら、どうしてこんなに時間がかかるんだ。」
「どうも死にたくなさそうだ。」
そうこうしているうちに、日もすっかり暮れました。僧は舟の中で立ち上がりました。
「いよいよだぞ、お坊さんが川に飛び込むぞ!」みんな大声を上げて、手を叩きました。
 僧は、衣(ころも)を脱いで褌(ふんどし)一丁になると、合掌したまま足から川に飛び込みました。
僧の身体は一度は水の中に沈みましたが、浮かび上がり、また沈み、それからぷかっと浮かび上がりました。そして川岸に向かって手足をばたつかせ始めました。
「どうやらこの坊さんは、自分で言ったことを今は後悔しているんだ。この世にまだ未練があるようだ。」
一人が、そう言って、僧の両手を掴み、岸に引き揚げてやりました。
僧は、両手を合わせて、その人に言いました。
「命を救っていただき有り難うございました。ご恩は決して忘れません。このお返しはあの世で必ずいたします。」
人々は愛想をつかし、お坊さんの悪口を言い始めました。
「何ってくそ坊主!」
「最初から身投げしようなんて気はなかったのだろう。」
「まんまと騙された。」
中には小石を拾うと僧に向かって投げつける者もいました。
「あいた!痛たた!」
まっ裸のままの僧侶は、頭を自分の手でかばいながら逃げていきました。(Kudos) 原作「宇治拾遺物語」より
僧は、衣(ころも)を脱いで褌(ふんどし)一丁になると、合掌したまま足から川に飛び込みました。
僧の身体は一度は水の中に沈みましたが、浮かび上がり、また沈み、それからぷかっと浮かび上がりました。そして川岸に向かって手足をばたつかせ始めました。
「どうやらこの坊さんは、自分で言ったことを今は後悔しているんだ。この世にまだ未練があるようだ。」
一人が、そう言って、僧の両手を掴み、岸に引き揚げてやりました。
僧は、両手を合わせて、その人に言いました。
「命を救っていただき有り難うございました。ご恩は決して忘れません。このお返しはあの世で必ずいたします。」
人々は愛想をつかし、お坊さんの悪口を言い始めました。
「何ってくそ坊主!」
「最初から身投げしようなんて気はなかったのだろう。」
「まんまと騙された。」
中には小石を拾うと僧に向かって投げつける者もいました。
「あいた!痛たた!」
まっ裸のままの僧侶は、頭を自分の手でかばいながら逃げていきました。(Kudos) 原作「宇治拾遺物語」より
