

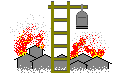 日本では、ほとんどの人が木造家屋に住んでいます。江戸時代、江戸(東京)ではそんな家が密集していました。ですから一旦火事が起これば、またたく間に広がりました。当時の大火に「天和の大火」別名「お七火事」というのがあります。
むかし、江戸は本郷というところに、八百屋を営む八兵衛というものがおり、妻と十六歳になる娘のお七と暮していました。お七は十六にしては大人びていました。
天和二年(1682年)暮れ、近くの寺から火が出て瞬く間に燃え広がった。
「火事だ!火事だ!」人々は叫び、逃げ惑いました。
八兵衛は妻と娘のお七をせかせて家から出ました。
「風が強くなってきた。大火事になるぞ。それに風下だ。ここにいると危ない。吉祥寺に逃げるぞ。」
(吉祥寺は駒込にある檀那寺でした。)
「急げ、火が来るぞ!休むな!」お七に言いました。
お七は両親について必死に走りました。
火事は正午ごろ出火したのですが、翌朝の五時ごろようやく鎮火しました。この火事で三千五百人以上の人が犠牲になったそうです。
吉祥寺では逃げてきた人々でもうごった返しでした。母親は、部屋の隅で指のとげを抜こうとしている若者をふと目にして娘に言いました。
「お七、あそこの若い人、何か困っているようですね。指にとげでも刺さったのでしょう。行って、抜いておあげ。私は和尚さんに挨拶してきますから。」
娘は若者に近づき、声をかけ、手を取って診てみました。
しばらくして、
「取れましたわ!もう痛くありませんこと?」
若者は顔をほころばせて言いました。
「ああ、ありがとう。もう大丈夫。」
若者は、和尚さんの元で働いていました。和尚さんは、この若者の面倒見てくれ、と親から頼まれたのです。
二人は、手を取り合ったまま、しばらく見つめ合いました。どうやら恋に落ちたようです。
「お七、お七、戻りましたよ。」母の声が聞こえました。
「そうですか。お七さんというのですね。吉三郎です。」
「吉三郎さま?吉さまとお呼びしてもよろしいかしら?」
「かまいませんよ。もう少しお七さんのことが知りたいなあ。文に書いて庭の大きな石の下に入れて下さい。」
「ええ、そうしますわ。」お七は母の所へ戻りました。
お七と両親は、家を建て直す間、お寺で生活しなければなりませんでした。でもお七にとってはあの若者と密かに文を交わす幸せな日々でした。庭の大きな石の下に若者からの文がありました。お七はかわりに自分の文をそこに隠しました。
日本では、ほとんどの人が木造家屋に住んでいます。江戸時代、江戸(東京)ではそんな家が密集していました。ですから一旦火事が起これば、またたく間に広がりました。当時の大火に「天和の大火」別名「お七火事」というのがあります。
むかし、江戸は本郷というところに、八百屋を営む八兵衛というものがおり、妻と十六歳になる娘のお七と暮していました。お七は十六にしては大人びていました。
天和二年(1682年)暮れ、近くの寺から火が出て瞬く間に燃え広がった。
「火事だ!火事だ!」人々は叫び、逃げ惑いました。
八兵衛は妻と娘のお七をせかせて家から出ました。
「風が強くなってきた。大火事になるぞ。それに風下だ。ここにいると危ない。吉祥寺に逃げるぞ。」
(吉祥寺は駒込にある檀那寺でした。)
「急げ、火が来るぞ!休むな!」お七に言いました。
お七は両親について必死に走りました。
火事は正午ごろ出火したのですが、翌朝の五時ごろようやく鎮火しました。この火事で三千五百人以上の人が犠牲になったそうです。
吉祥寺では逃げてきた人々でもうごった返しでした。母親は、部屋の隅で指のとげを抜こうとしている若者をふと目にして娘に言いました。
「お七、あそこの若い人、何か困っているようですね。指にとげでも刺さったのでしょう。行って、抜いておあげ。私は和尚さんに挨拶してきますから。」
娘は若者に近づき、声をかけ、手を取って診てみました。
しばらくして、
「取れましたわ!もう痛くありませんこと?」
若者は顔をほころばせて言いました。
「ああ、ありがとう。もう大丈夫。」
若者は、和尚さんの元で働いていました。和尚さんは、この若者の面倒見てくれ、と親から頼まれたのです。
二人は、手を取り合ったまま、しばらく見つめ合いました。どうやら恋に落ちたようです。
「お七、お七、戻りましたよ。」母の声が聞こえました。
「そうですか。お七さんというのですね。吉三郎です。」
「吉三郎さま?吉さまとお呼びしてもよろしいかしら?」
「かまいませんよ。もう少しお七さんのことが知りたいなあ。文に書いて庭の大きな石の下に入れて下さい。」
「ええ、そうしますわ。」お七は母の所へ戻りました。
お七と両親は、家を建て直す間、お寺で生活しなければなりませんでした。でもお七にとってはあの若者と密かに文を交わす幸せな日々でした。庭の大きな石の下に若者からの文がありました。お七はかわりに自分の文をそこに隠しました。
お七さま あなたをどんなに愛しく思い、どんなに会いたいと思っていることか。 同じ所にいながら話しもできないとは何とせつないことでしょう。 吉三郎 |
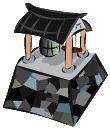 ゴオーーーン!
お七は布団から身を起こしました。
「もうすぐ夜が明けますわ。戻らなくては。」
吉三郎はお七の手をとりました。
「お七、また会えたらいいなあ。」
「吉さま、また会えますとも。きっと。」
天和3年(1683年)、家の再建も終わり、八兵衛一家は寺を出ることになりました。八兵衛は和尚さんの所に挨拶に行きました。
「大変お世話になりました。」
「とんでもない。仏に仕える身が困った人を助けるのは当然のことです。家に帰れてよかったですね。」
でもお七にはうれしくないことでした。吉三郎と別れたくありません。吉三郎は、お七がその日の朝帰るのを知っていました。声をかけたかったのですが、遠くから見送っただけでした。
「お七さん...」とささやきました。
お七は名がよばれた気がして、振り返りましたが、誰もいませんでした。(Kudos)
ゴオーーーン!
お七は布団から身を起こしました。
「もうすぐ夜が明けますわ。戻らなくては。」
吉三郎はお七の手をとりました。
「お七、また会えたらいいなあ。」
「吉さま、また会えますとも。きっと。」
天和3年(1683年)、家の再建も終わり、八兵衛一家は寺を出ることになりました。八兵衛は和尚さんの所に挨拶に行きました。
「大変お世話になりました。」
「とんでもない。仏に仕える身が困った人を助けるのは当然のことです。家に帰れてよかったですね。」
でもお七にはうれしくないことでした。吉三郎と別れたくありません。吉三郎は、お七がその日の朝帰るのを知っていました。声をかけたかったのですが、遠くから見送っただけでした。
「お七さん...」とささやきました。
お七は名がよばれた気がして、振り返りましたが、誰もいませんでした。(Kudos)
(続く)
