
炭焼き長者
奈良興福寺
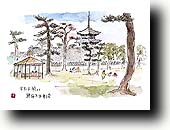 大分県の臼杵を訪れることがありましたら、ぜひ山肌に彫られた石仏を訪ねて見て下さい。この石仏にまつわる悲しい物語をお話しましょう。
むかし、むかし、ある所に、玉津姫というとても美しい娘さんがおりました。父親は当時の都、奈良の宮廷貴族の一人でありました。
娘さんが年頃になった頃のことです。顔に黒いあざができ、しばらくすると、その透き通るような白い肌は黒ずんでしまいました。もう娘さんを美しいと思う人は誰もいなくなってしまい、結婚を申し出る者ももちろんいなくなってしまいました。
両親もたいそう心配し、奈良の三輪神社にお参りに行くようすすめました。
娘さんは、神社にお篭もりし良い縁談があるように願をかけることにしました。水垢離(みずごり)をし、七日間飲まず食わず、ひたすら祈り続けました。そして満願の夜のことです。夢枕に神様が現れ、こう言いました。
「豊後(今の大分県)のあたりに、小五郎と言う炭焼きがおる。彼こそお前の夫となる者である。この人と夫婦になれば、お前たちは共に金持ちになるであろう。」
そして神様は、娘さんの頭の先からつま先まで杉の葉でお払いをすると、消えてしまいました。眠りから目が覚めると、娘さんの髪には杉の葉がさしてありました。
思っても見なかったことでしたが、神様のお告げを信じました。
家に戻ってからも、豊後に行くという思いは薄れることはありませんでした。そこでこっそりと家を抜け出し、一人はるばる豊後に向かいました。それは長く、辛い旅でした。ひたすら歩いて、そして船に乗りました。やっとのことで船は、豊後につきました。そこで小五郎と言う人に会えると娘は信じていました。
しかし、彼の居場所もわからず途方に暮れていると、一人の老婆が目の前に現れ、こう言いました。
「小五郎のいる所なら知ってるよ。しかしもう遅い。今夜はわたしの家に泊まりなさい。明日、連れて行ってあげよう。」
次の日、老婆は娘さんを一軒のあばら家につれて行くと、いつしか姿が見えなくなりました。その家に人気はなく、しばらく待つことにしました。やがて、一人の若者が帰ってきました。顔も腕も脚も日焼けしていて真っ黒でした。彼こそ探している人なのか、名前を尋ね、そして奈良から単身ここまでやってきたわけを話しました。「若者が自分の夫になる。」と娘が信じているので、若者は驚きました。
「わたしは貧しい炭焼き。二人で暮らす米も味噌もありません。お前さんと夫婦になるなんてとんでもないことです。」
娘さんは持参した硬貨を数枚彼に渡すと、こう言いました。
大分県の臼杵を訪れることがありましたら、ぜひ山肌に彫られた石仏を訪ねて見て下さい。この石仏にまつわる悲しい物語をお話しましょう。
むかし、むかし、ある所に、玉津姫というとても美しい娘さんがおりました。父親は当時の都、奈良の宮廷貴族の一人でありました。
娘さんが年頃になった頃のことです。顔に黒いあざができ、しばらくすると、その透き通るような白い肌は黒ずんでしまいました。もう娘さんを美しいと思う人は誰もいなくなってしまい、結婚を申し出る者ももちろんいなくなってしまいました。
両親もたいそう心配し、奈良の三輪神社にお参りに行くようすすめました。
娘さんは、神社にお篭もりし良い縁談があるように願をかけることにしました。水垢離(みずごり)をし、七日間飲まず食わず、ひたすら祈り続けました。そして満願の夜のことです。夢枕に神様が現れ、こう言いました。
「豊後(今の大分県)のあたりに、小五郎と言う炭焼きがおる。彼こそお前の夫となる者である。この人と夫婦になれば、お前たちは共に金持ちになるであろう。」
そして神様は、娘さんの頭の先からつま先まで杉の葉でお払いをすると、消えてしまいました。眠りから目が覚めると、娘さんの髪には杉の葉がさしてありました。
思っても見なかったことでしたが、神様のお告げを信じました。
家に戻ってからも、豊後に行くという思いは薄れることはありませんでした。そこでこっそりと家を抜け出し、一人はるばる豊後に向かいました。それは長く、辛い旅でした。ひたすら歩いて、そして船に乗りました。やっとのことで船は、豊後につきました。そこで小五郎と言う人に会えると娘は信じていました。
しかし、彼の居場所もわからず途方に暮れていると、一人の老婆が目の前に現れ、こう言いました。
「小五郎のいる所なら知ってるよ。しかしもう遅い。今夜はわたしの家に泊まりなさい。明日、連れて行ってあげよう。」
次の日、老婆は娘さんを一軒のあばら家につれて行くと、いつしか姿が見えなくなりました。その家に人気はなく、しばらく待つことにしました。やがて、一人の若者が帰ってきました。顔も腕も脚も日焼けしていて真っ黒でした。彼こそ探している人なのか、名前を尋ね、そして奈良から単身ここまでやってきたわけを話しました。「若者が自分の夫になる。」と娘が信じているので、若者は驚きました。
「わたしは貧しい炭焼き。二人で暮らす米も味噌もありません。お前さんと夫婦になるなんてとんでもないことです。」
娘さんは持参した硬貨を数枚彼に渡すと、こう言いました。
 「このお金で必要なものを買ってきて下さい。米や味噌も。」
実は彼は今までお金という物を持ったこともなければ見たこともありませんでした。お金が価値のあるものであるということも知りませんでした。
お金を持って町に行く途中、淵で数羽のかもを見ました。晩飯用に数羽捕まえようと思いました。
「弓矢を持ってくればよかったなあ。待てよ。ここに金がある。かもに投げてみよう。」
一羽のかもめがけてお金を投げてみました。かもは甲高い声を上げると飛び去ってしまいました。別のかもにも投げてみました。またも失敗です。結局、獲物はつかまらず有り金全部投げてしまいました。
若者は、結局、その日の午後手ぶらで家に戻りました。娘さんは、彼の子供じみた振る舞いに呆れ、母親のような調子で言いました。
「お前さま、お金がどんなに大切なものかわからないのですね。いいですか、お金があれば、ほしい物は何でも買えるのですよ。でもお前さまは私が持ってきたお金を全部投げてしまいましたね。」
娘さんは小言を言うのをやめると、しばらくじっと彼の顔を見つめました。
若者は詫びるどころか、無邪気にこう言いました。
「お金なんて値打ちのあるものじゃない。わたしは黄色い砂と石が山になっている所を知っている。お前さんに見せてやろう。」
彼は、最初に炭焼き小屋に、そして次に、かもにお金を投げた淵へ彼女を連れて行きました。彼の話したことは決して大げさではありませんでした。炭窯の灰の中に金の塊が幾つかころがっていましたし、水底には砂金の層がありました。
娘さんはとても驚き、水をすくうと顔を洗いました。水に映ったわが身を見て、喜びの声を上げました。顔中にあった黒いあざが消えているのです。水に映っているのは昔の美しかった自分でした。若者も顔を洗うと、そこには男前の若者がいました。とても凛々しく見えました。二人はとても嬉しい気分になり、砂金と金塊を集めました。やがて二人は金持ちになり、周りの者は彼のことを「炭焼き長者」と呼ぶようになりました。
まもなく二人に子供が産まれ、般若姫と名づけられました。歳を重ねるごとに、それは、それは美しい女の子に成長しました。その評判は国中に広まっていきました。
さて、奈良の都に皇子がおりました。皇子の父、帝は、息子とその姫こそ似合いの夫婦になると考えました。しかし、長者さんは、一人娘ゆえ求婚に承諾しませんでした。皇子はたいそうがっかりしましたが、姫に会いたい気持ちは変わりません。そこで姫に会うための長旅に出ました。牛飼いに変装し、長者さんの住み込みの牛飼いとして働くことになりました。
そして結局は運命が二人を結び付けたのです。姫はまもなく彼との恋に落ちました。
姫から子供が出来たと告げられた皇子は、自分こそ帝の四番目の子であると皆に発表するべき時が来たと思いました。そして、姫の父親にこの結婚を認めてくれるようお願いしました。
長者さんは、しぶしぶ承諾するしかありませんでした。皇子は、さっそく二人で都に戻りたいと思いました。高まる気持ちの中、皇子は身重の妻より一足早く都に出航しました。
出産後、新しい生活への希望に満ち溢れて、皇妃は船出しました。しかし、長者さん夫婦は悲しみに浸っていました。最後に出来る事といえ
「このお金で必要なものを買ってきて下さい。米や味噌も。」
実は彼は今までお金という物を持ったこともなければ見たこともありませんでした。お金が価値のあるものであるということも知りませんでした。
お金を持って町に行く途中、淵で数羽のかもを見ました。晩飯用に数羽捕まえようと思いました。
「弓矢を持ってくればよかったなあ。待てよ。ここに金がある。かもに投げてみよう。」
一羽のかもめがけてお金を投げてみました。かもは甲高い声を上げると飛び去ってしまいました。別のかもにも投げてみました。またも失敗です。結局、獲物はつかまらず有り金全部投げてしまいました。
若者は、結局、その日の午後手ぶらで家に戻りました。娘さんは、彼の子供じみた振る舞いに呆れ、母親のような調子で言いました。
「お前さま、お金がどんなに大切なものかわからないのですね。いいですか、お金があれば、ほしい物は何でも買えるのですよ。でもお前さまは私が持ってきたお金を全部投げてしまいましたね。」
娘さんは小言を言うのをやめると、しばらくじっと彼の顔を見つめました。
若者は詫びるどころか、無邪気にこう言いました。
「お金なんて値打ちのあるものじゃない。わたしは黄色い砂と石が山になっている所を知っている。お前さんに見せてやろう。」
彼は、最初に炭焼き小屋に、そして次に、かもにお金を投げた淵へ彼女を連れて行きました。彼の話したことは決して大げさではありませんでした。炭窯の灰の中に金の塊が幾つかころがっていましたし、水底には砂金の層がありました。
娘さんはとても驚き、水をすくうと顔を洗いました。水に映ったわが身を見て、喜びの声を上げました。顔中にあった黒いあざが消えているのです。水に映っているのは昔の美しかった自分でした。若者も顔を洗うと、そこには男前の若者がいました。とても凛々しく見えました。二人はとても嬉しい気分になり、砂金と金塊を集めました。やがて二人は金持ちになり、周りの者は彼のことを「炭焼き長者」と呼ぶようになりました。
まもなく二人に子供が産まれ、般若姫と名づけられました。歳を重ねるごとに、それは、それは美しい女の子に成長しました。その評判は国中に広まっていきました。
さて、奈良の都に皇子がおりました。皇子の父、帝は、息子とその姫こそ似合いの夫婦になると考えました。しかし、長者さんは、一人娘ゆえ求婚に承諾しませんでした。皇子はたいそうがっかりしましたが、姫に会いたい気持ちは変わりません。そこで姫に会うための長旅に出ました。牛飼いに変装し、長者さんの住み込みの牛飼いとして働くことになりました。
そして結局は運命が二人を結び付けたのです。姫はまもなく彼との恋に落ちました。
姫から子供が出来たと告げられた皇子は、自分こそ帝の四番目の子であると皆に発表するべき時が来たと思いました。そして、姫の父親にこの結婚を認めてくれるようお願いしました。
長者さんは、しぶしぶ承諾するしかありませんでした。皇子は、さっそく二人で都に戻りたいと思いました。高まる気持ちの中、皇子は身重の妻より一足早く都に出航しました。
出産後、新しい生活への希望に満ち溢れて、皇妃は船出しました。しかし、長者さん夫婦は悲しみに浸っていました。最後に出来る事といえ
 ば山の上から娘の船を見送ることだけでした。娘の幸せな新婚生活を心から願いました。そして、自分たちの寂しさを何とか抑えようとしました。船はゆっくりと、一波ごとに、だんだんとその形は小さくなり、ついには地平線のかなたへと消え
てしまいました。二人はじっと立ち尽くし、しばらく海を眺めていました。
二人は娘からのたよりを心待ちにしていました。しかし、届いたたよりは、船が嵐に襲われた、というものでした。両親の悲しみはいかほどだったことでしょうか。二人の心は悲しみで引き裂かれたに違いありません。
長者さんは臼杵に堂を五つ建てさせました。そして娘の魂を弔うため、百体の石仏を山の斜面に彫らせました。その辺りは真名原と呼ばれていたので、長者さんは後に「真名野長者」と呼ばれるようになりました。
長者さんは97歳、妻は91歳で亡くなったそうです。二人の木像が、かわいそうな般若姫のために建てられた満月寺に安置されたということです。
ば山の上から娘の船を見送ることだけでした。娘の幸せな新婚生活を心から願いました。そして、自分たちの寂しさを何とか抑えようとしました。船はゆっくりと、一波ごとに、だんだんとその形は小さくなり、ついには地平線のかなたへと消え
てしまいました。二人はじっと立ち尽くし、しばらく海を眺めていました。
二人は娘からのたよりを心待ちにしていました。しかし、届いたたよりは、船が嵐に襲われた、というものでした。両親の悲しみはいかほどだったことでしょうか。二人の心は悲しみで引き裂かれたに違いありません。
長者さんは臼杵に堂を五つ建てさせました。そして娘の魂を弔うため、百体の石仏を山の斜面に彫らせました。その辺りは真名原と呼ばれていたので、長者さんは後に「真名野長者」と呼ばれるようになりました。
長者さんは97歳、妻は91歳で亡くなったそうです。二人の木像が、かわいそうな般若姫のために建てられた満月寺に安置されたということです。
真名野長者夫妻像
(By Kudo:2003.11.27)



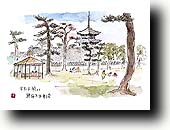 大分県の臼杵を訪れることがありましたら、ぜひ山肌に彫られた石仏を訪ねて見て下さい。この石仏にまつわる悲しい物語をお話しましょう。
むかし、むかし、ある所に、玉津姫というとても美しい娘さんがおりました。父親は当時の都、奈良の宮廷貴族の一人でありました。
娘さんが年頃になった頃のことです。顔に黒いあざができ、しばらくすると、その透き通るような白い肌は黒ずんでしまいました。もう娘さんを美しいと思う人は誰もいなくなってしまい、結婚を申し出る者ももちろんいなくなってしまいました。
両親もたいそう心配し、奈良の三輪神社にお参りに行くようすすめました。
娘さんは、神社にお篭もりし良い縁談があるように願をかけることにしました。水垢離(みずごり)をし、七日間飲まず食わず、ひたすら祈り続けました。そして満願の夜のことです。夢枕に神様が現れ、こう言いました。
「豊後(今の大分県)のあたりに、小五郎と言う炭焼きがおる。彼こそお前の夫となる者である。この人と夫婦になれば、お前たちは共に金持ちになるであろう。」
そして神様は、娘さんの頭の先からつま先まで杉の葉でお払いをすると、消えてしまいました。眠りから目が覚めると、娘さんの髪には杉の葉がさしてありました。
思っても見なかったことでしたが、神様のお告げを信じました。
家に戻ってからも、豊後に行くという思いは薄れることはありませんでした。そこでこっそりと家を抜け出し、一人はるばる豊後に向かいました。それは長く、辛い旅でした。ひたすら歩いて、そして船に乗りました。やっとのことで船は、豊後につきました。そこで小五郎と言う人に会えると娘は信じていました。
しかし、彼の居場所もわからず途方に暮れていると、一人の老婆が目の前に現れ、こう言いました。
「小五郎のいる所なら知ってるよ。しかしもう遅い。今夜はわたしの家に泊まりなさい。明日、連れて行ってあげよう。」
次の日、老婆は娘さんを一軒のあばら家につれて行くと、いつしか姿が見えなくなりました。その家に人気はなく、しばらく待つことにしました。やがて、一人の若者が帰ってきました。顔も腕も脚も日焼けしていて真っ黒でした。彼こそ探している人なのか、名前を尋ね、そして奈良から単身ここまでやってきたわけを話しました。「若者が自分の夫になる。」と娘が信じているので、若者は驚きました。
「わたしは貧しい炭焼き。二人で暮らす米も味噌もありません。お前さんと夫婦になるなんてとんでもないことです。」
娘さんは持参した硬貨を数枚彼に渡すと、こう言いました。
大分県の臼杵を訪れることがありましたら、ぜひ山肌に彫られた石仏を訪ねて見て下さい。この石仏にまつわる悲しい物語をお話しましょう。
むかし、むかし、ある所に、玉津姫というとても美しい娘さんがおりました。父親は当時の都、奈良の宮廷貴族の一人でありました。
娘さんが年頃になった頃のことです。顔に黒いあざができ、しばらくすると、その透き通るような白い肌は黒ずんでしまいました。もう娘さんを美しいと思う人は誰もいなくなってしまい、結婚を申し出る者ももちろんいなくなってしまいました。
両親もたいそう心配し、奈良の三輪神社にお参りに行くようすすめました。
娘さんは、神社にお篭もりし良い縁談があるように願をかけることにしました。水垢離(みずごり)をし、七日間飲まず食わず、ひたすら祈り続けました。そして満願の夜のことです。夢枕に神様が現れ、こう言いました。
「豊後(今の大分県)のあたりに、小五郎と言う炭焼きがおる。彼こそお前の夫となる者である。この人と夫婦になれば、お前たちは共に金持ちになるであろう。」
そして神様は、娘さんの頭の先からつま先まで杉の葉でお払いをすると、消えてしまいました。眠りから目が覚めると、娘さんの髪には杉の葉がさしてありました。
思っても見なかったことでしたが、神様のお告げを信じました。
家に戻ってからも、豊後に行くという思いは薄れることはありませんでした。そこでこっそりと家を抜け出し、一人はるばる豊後に向かいました。それは長く、辛い旅でした。ひたすら歩いて、そして船に乗りました。やっとのことで船は、豊後につきました。そこで小五郎と言う人に会えると娘は信じていました。
しかし、彼の居場所もわからず途方に暮れていると、一人の老婆が目の前に現れ、こう言いました。
「小五郎のいる所なら知ってるよ。しかしもう遅い。今夜はわたしの家に泊まりなさい。明日、連れて行ってあげよう。」
次の日、老婆は娘さんを一軒のあばら家につれて行くと、いつしか姿が見えなくなりました。その家に人気はなく、しばらく待つことにしました。やがて、一人の若者が帰ってきました。顔も腕も脚も日焼けしていて真っ黒でした。彼こそ探している人なのか、名前を尋ね、そして奈良から単身ここまでやってきたわけを話しました。「若者が自分の夫になる。」と娘が信じているので、若者は驚きました。
「わたしは貧しい炭焼き。二人で暮らす米も味噌もありません。お前さんと夫婦になるなんてとんでもないことです。」
娘さんは持参した硬貨を数枚彼に渡すと、こう言いました。
 「このお金で必要なものを買ってきて下さい。米や味噌も。」
実は彼は今までお金という物を持ったこともなければ見たこともありませんでした。お金が価値のあるものであるということも知りませんでした。
お金を持って町に行く途中、淵で数羽のかもを見ました。晩飯用に数羽捕まえようと思いました。
「弓矢を持ってくればよかったなあ。待てよ。ここに金がある。かもに投げてみよう。」
一羽のかもめがけてお金を投げてみました。かもは甲高い声を上げると飛び去ってしまいました。別のかもにも投げてみました。またも失敗です。結局、獲物はつかまらず有り金全部投げてしまいました。
若者は、結局、その日の午後手ぶらで家に戻りました。娘さんは、彼の子供じみた振る舞いに呆れ、母親のような調子で言いました。
「お前さま、お金がどんなに大切なものかわからないのですね。いいですか、お金があれば、ほしい物は何でも買えるのですよ。でもお前さまは私が持ってきたお金を全部投げてしまいましたね。」
娘さんは小言を言うのをやめると、しばらくじっと彼の顔を見つめました。
若者は詫びるどころか、無邪気にこう言いました。
「お金なんて値打ちのあるものじゃない。わたしは黄色い砂と石が山になっている所を知っている。お前さんに見せてやろう。」
彼は、最初に炭焼き小屋に、そして次に、かもにお金を投げた淵へ彼女を連れて行きました。彼の話したことは決して大げさではありませんでした。炭窯の灰の中に金の塊が幾つかころがっていましたし、水底には砂金の層がありました。
娘さんはとても驚き、水をすくうと顔を洗いました。水に映ったわが身を見て、喜びの声を上げました。顔中にあった黒いあざが消えているのです。水に映っているのは昔の美しかった自分でした。若者も顔を洗うと、そこには男前の若者がいました。とても凛々しく見えました。二人はとても嬉しい気分になり、砂金と金塊を集めました。やがて二人は金持ちになり、周りの者は彼のことを「炭焼き長者」と呼ぶようになりました。
まもなく二人に子供が産まれ、般若姫と名づけられました。歳を重ねるごとに、それは、それは美しい女の子に成長しました。その評判は国中に広まっていきました。
さて、奈良の都に皇子がおりました。皇子の父、帝は、息子とその姫こそ似合いの夫婦になると考えました。しかし、長者さんは、一人娘ゆえ求婚に承諾しませんでした。皇子はたいそうがっかりしましたが、姫に会いたい気持ちは変わりません。そこで姫に会うための長旅に出ました。牛飼いに変装し、長者さんの住み込みの牛飼いとして働くことになりました。
そして結局は運命が二人を結び付けたのです。姫はまもなく彼との恋に落ちました。
姫から子供が出来たと告げられた皇子は、自分こそ帝の四番目の子であると皆に発表するべき時が来たと思いました。そして、姫の父親にこの結婚を認めてくれるようお願いしました。
長者さんは、しぶしぶ承諾するしかありませんでした。皇子は、さっそく二人で都に戻りたいと思いました。高まる気持ちの中、皇子は身重の妻より一足早く都に出航しました。
出産後、新しい生活への希望に満ち溢れて、皇妃は船出しました。しかし、長者さん夫婦は悲しみに浸っていました。最後に出来る事といえ
「このお金で必要なものを買ってきて下さい。米や味噌も。」
実は彼は今までお金という物を持ったこともなければ見たこともありませんでした。お金が価値のあるものであるということも知りませんでした。
お金を持って町に行く途中、淵で数羽のかもを見ました。晩飯用に数羽捕まえようと思いました。
「弓矢を持ってくればよかったなあ。待てよ。ここに金がある。かもに投げてみよう。」
一羽のかもめがけてお金を投げてみました。かもは甲高い声を上げると飛び去ってしまいました。別のかもにも投げてみました。またも失敗です。結局、獲物はつかまらず有り金全部投げてしまいました。
若者は、結局、その日の午後手ぶらで家に戻りました。娘さんは、彼の子供じみた振る舞いに呆れ、母親のような調子で言いました。
「お前さま、お金がどんなに大切なものかわからないのですね。いいですか、お金があれば、ほしい物は何でも買えるのですよ。でもお前さまは私が持ってきたお金を全部投げてしまいましたね。」
娘さんは小言を言うのをやめると、しばらくじっと彼の顔を見つめました。
若者は詫びるどころか、無邪気にこう言いました。
「お金なんて値打ちのあるものじゃない。わたしは黄色い砂と石が山になっている所を知っている。お前さんに見せてやろう。」
彼は、最初に炭焼き小屋に、そして次に、かもにお金を投げた淵へ彼女を連れて行きました。彼の話したことは決して大げさではありませんでした。炭窯の灰の中に金の塊が幾つかころがっていましたし、水底には砂金の層がありました。
娘さんはとても驚き、水をすくうと顔を洗いました。水に映ったわが身を見て、喜びの声を上げました。顔中にあった黒いあざが消えているのです。水に映っているのは昔の美しかった自分でした。若者も顔を洗うと、そこには男前の若者がいました。とても凛々しく見えました。二人はとても嬉しい気分になり、砂金と金塊を集めました。やがて二人は金持ちになり、周りの者は彼のことを「炭焼き長者」と呼ぶようになりました。
まもなく二人に子供が産まれ、般若姫と名づけられました。歳を重ねるごとに、それは、それは美しい女の子に成長しました。その評判は国中に広まっていきました。
さて、奈良の都に皇子がおりました。皇子の父、帝は、息子とその姫こそ似合いの夫婦になると考えました。しかし、長者さんは、一人娘ゆえ求婚に承諾しませんでした。皇子はたいそうがっかりしましたが、姫に会いたい気持ちは変わりません。そこで姫に会うための長旅に出ました。牛飼いに変装し、長者さんの住み込みの牛飼いとして働くことになりました。
そして結局は運命が二人を結び付けたのです。姫はまもなく彼との恋に落ちました。
姫から子供が出来たと告げられた皇子は、自分こそ帝の四番目の子であると皆に発表するべき時が来たと思いました。そして、姫の父親にこの結婚を認めてくれるようお願いしました。
長者さんは、しぶしぶ承諾するしかありませんでした。皇子は、さっそく二人で都に戻りたいと思いました。高まる気持ちの中、皇子は身重の妻より一足早く都に出航しました。
出産後、新しい生活への希望に満ち溢れて、皇妃は船出しました。しかし、長者さん夫婦は悲しみに浸っていました。最後に出来る事といえ
 ば山の上から娘の船を見送ることだけでした。娘の幸せな新婚生活を心から願いました。そして、自分たちの寂しさを何とか抑えようとしました。船はゆっくりと、一波ごとに、だんだんとその形は小さくなり、ついには地平線のかなたへと消え
てしまいました。二人はじっと立ち尽くし、しばらく海を眺めていました。
二人は娘からのたよりを心待ちにしていました。しかし、届いたたよりは、船が嵐に襲われた、というものでした。両親の悲しみはいかほどだったことでしょうか。二人の心は悲しみで引き裂かれたに違いありません。
長者さんは臼杵に堂を五つ建てさせました。そして娘の魂を弔うため、百体の石仏を山の斜面に彫らせました。その辺りは真名原と呼ばれていたので、長者さんは後に「真名野長者」と呼ばれるようになりました。
長者さんは97歳、妻は91歳で亡くなったそうです。二人の木像が、かわいそうな般若姫のために建てられた満月寺に安置されたということです。
ば山の上から娘の船を見送ることだけでした。娘の幸せな新婚生活を心から願いました。そして、自分たちの寂しさを何とか抑えようとしました。船はゆっくりと、一波ごとに、だんだんとその形は小さくなり、ついには地平線のかなたへと消え
てしまいました。二人はじっと立ち尽くし、しばらく海を眺めていました。
二人は娘からのたよりを心待ちにしていました。しかし、届いたたよりは、船が嵐に襲われた、というものでした。両親の悲しみはいかほどだったことでしょうか。二人の心は悲しみで引き裂かれたに違いありません。
長者さんは臼杵に堂を五つ建てさせました。そして娘の魂を弔うため、百体の石仏を山の斜面に彫らせました。その辺りは真名原と呼ばれていたので、長者さんは後に「真名野長者」と呼ばれるようになりました。
長者さんは97歳、妻は91歳で亡くなったそうです。二人の木像が、かわいそうな般若姫のために建てられた満月寺に安置されたということです。
