
牛若と弁慶
12世紀、平安末期の日本では、平家は栄華を極め、源氏は滅亡寸前でありました。そんな中、京の都の橋の上で、ある出会いがありました。
 五条の橋の上、小脇になぎなた(にほんのやり)を抱えた、一際大きな僧が、仁王のごとく、立っていました。明るい月が、五条の橋を照らし出していました。※なぎなた(幅広で反りの強い刀身に長い柄をつけた武器)
おや、大男の方へ、笛を吹き近づいて来る者がいます。何と美しい笛の音でしょう。薄での絹の着物を被いて(かずいて)いるのでその顔ははっきりわかりません。腰に差している太刀は由緒あるものに見えます。大男は、その立派な太刀に目をつけました。男は、笛吹きに向かって大音声を上げました。
「拙僧の宿願は千本の太刀を得ること。すでに999本の太刀を得た。あと一本で満願成就。」
しかし笛吹きは、一向に動じることなく笛を吹きながら、大男の脇を通り過ぎようとしました。
「おい、ちょっと待て。今も話したように、拙僧の宿願は千本の太刀。あと一本で満願成就だ。そちは見事な太刀を差しておる。それを拙僧に即座によこすなら、命は助けてやる。どこへなりと立ち去れ。」
その人は笛を吹くのを止め、被きものを取ります。何と気高い、きりりとした顔立ちの若者でしょう。
若者は、穏やかに、落ち着いた声で話します。
「そちが999本の太刀を集めたのは真実(まこと)か。しかし、そちがやっていることは盗みに他ならぬ。」
男は大声で叫びます。
「だまれ!お前が、太刀をよこさぬと言うなら、力ずくでも頂くまでだ。もうわしのものも同然だ。」
若者はおどしに動ずることなく、
「取れるものなら取ってみよ。」
男は、なぎなたを頭の上に振りかざし、若者を威嚇します。いつもなら、ここで大方の者は恐れをなし、太刀を捨てて逃げ出します。しかし、若者にその気配は全くなく、大男の攻撃をすばやくかわします。男のなぎなたが空を切ると、男はちょっと取り乱し、もう一度切りかかります。しかし若者を見失ってしまいます。
「一体どこに行った。」と怒鳴ります。
「ここぞ。御坊。」後ろから声がしました。
「何をこしゃくな!」
男は怒りで顔が真っ赤になり、再び切りかかります。若者は、今度は鳥のように軽やかに飛び上がり、笛で男のなぎなたを叩き落し、橋の欄干に立ちます。男は、慌てて、なぎなたを拾おうとしますが、その前に、若者はなぎなたの上に飛び降ります。
「容易にわが太刀は奪えぬと知ったか。」若者は男に言います。
「参った。降参だ。貴殿は、この道では、名の通るお方とお見受けした。お名前をお明かし下され。拙僧は弁慶と申す僧兵だ。」弁慶は、自らの負けを潔く認めて、「これからは、そこもとの郎党になりましょう。」と言う。
五条の橋の上、小脇になぎなた(にほんのやり)を抱えた、一際大きな僧が、仁王のごとく、立っていました。明るい月が、五条の橋を照らし出していました。※なぎなた(幅広で反りの強い刀身に長い柄をつけた武器)
おや、大男の方へ、笛を吹き近づいて来る者がいます。何と美しい笛の音でしょう。薄での絹の着物を被いて(かずいて)いるのでその顔ははっきりわかりません。腰に差している太刀は由緒あるものに見えます。大男は、その立派な太刀に目をつけました。男は、笛吹きに向かって大音声を上げました。
「拙僧の宿願は千本の太刀を得ること。すでに999本の太刀を得た。あと一本で満願成就。」
しかし笛吹きは、一向に動じることなく笛を吹きながら、大男の脇を通り過ぎようとしました。
「おい、ちょっと待て。今も話したように、拙僧の宿願は千本の太刀。あと一本で満願成就だ。そちは見事な太刀を差しておる。それを拙僧に即座によこすなら、命は助けてやる。どこへなりと立ち去れ。」
その人は笛を吹くのを止め、被きものを取ります。何と気高い、きりりとした顔立ちの若者でしょう。
若者は、穏やかに、落ち着いた声で話します。
「そちが999本の太刀を集めたのは真実(まこと)か。しかし、そちがやっていることは盗みに他ならぬ。」
男は大声で叫びます。
「だまれ!お前が、太刀をよこさぬと言うなら、力ずくでも頂くまでだ。もうわしのものも同然だ。」
若者はおどしに動ずることなく、
「取れるものなら取ってみよ。」
男は、なぎなたを頭の上に振りかざし、若者を威嚇します。いつもなら、ここで大方の者は恐れをなし、太刀を捨てて逃げ出します。しかし、若者にその気配は全くなく、大男の攻撃をすばやくかわします。男のなぎなたが空を切ると、男はちょっと取り乱し、もう一度切りかかります。しかし若者を見失ってしまいます。
「一体どこに行った。」と怒鳴ります。
「ここぞ。御坊。」後ろから声がしました。
「何をこしゃくな!」
男は怒りで顔が真っ赤になり、再び切りかかります。若者は、今度は鳥のように軽やかに飛び上がり、笛で男のなぎなたを叩き落し、橋の欄干に立ちます。男は、慌てて、なぎなたを拾おうとしますが、その前に、若者はなぎなたの上に飛び降ります。
「容易にわが太刀は奪えぬと知ったか。」若者は男に言います。
「参った。降参だ。貴殿は、この道では、名の通るお方とお見受けした。お名前をお明かし下され。拙僧は弁慶と申す僧兵だ。」弁慶は、自らの負けを潔く認めて、「これからは、そこもとの郎党になりましょう。」と言う。
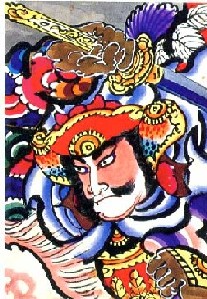 「私は牛若と申す。父、源義朝は源氏の棟領であったが、平治の乱で平家に滅ぼされた。いつの日か平家一族を倒したいと思っておる。それには私に仕える郎党が是非とも必要だ。そちにはわが郎党のかわきりになってもらおう。」
これは、「牛若」がその郎党となる「弁慶」に初めて出会った場面であります。後の源九郎判官義経(1159-1189)とは、この「牛若丸」でありました。「義経」が、兄「頼朝」と合流したのは、兄の平家討伐の富士川の戦いの直後でありました。兄弟は、平家一門を打ち、亡き父の無念を晴らすことを誓います。「弁慶」は人並はずれた老練、大力に加え、武術に秀でた人物と言われ、「義経」に従い源平合戦(1180-1185)に加わりました。
「義経」は平家滅亡に身をささげ、壇ノ浦の戦いで宿敵平家を壊滅し、悲願達成を果たした時、当然、兄「頼朝」からは長きにわたる辛い功労に対し労い(ねぎらい)の言葉があると思っていました。しかし、疑い深い「頼朝」は勝ち誇った「義経」が戻ってくるのを望みませんでした。日本で最初の武家政権「鎌倉幕府」を開いた「頼朝」ではありましたが、「義経」の鎌倉入りを許しませんでした。失意のどん底の「義経」は、「頼朝」に許しを請う書状(腰越状(こしごえじょう))を送りますが、結局は兄の敵意を強くさせるのみでした。「義経」は救いを、かつて若かりし時、一時身を寄せた奥州、藤原家に求めました。しかし当主「藤原秀衡」の死後、「頼朝」の圧力に屈した息子「泰衡」により自害を余儀なくされました。
驚くなかれ、今でも「義経」は日本人の中で人気のある歴史的英雄の一人であります。悲劇の英雄の象徴とされ、その死後でさえ、蝦夷(北海道)にいる、とかモンゴルに渡った、とか言ううわさ話が流れました。挙句の果てには、ジンギスカンと悲劇の英雄「義経」は同一人物である、という伝説まで生まれました。(2005.2.1 by Kudo/Image by Ohashi)
「私は牛若と申す。父、源義朝は源氏の棟領であったが、平治の乱で平家に滅ぼされた。いつの日か平家一族を倒したいと思っておる。それには私に仕える郎党が是非とも必要だ。そちにはわが郎党のかわきりになってもらおう。」
これは、「牛若」がその郎党となる「弁慶」に初めて出会った場面であります。後の源九郎判官義経(1159-1189)とは、この「牛若丸」でありました。「義経」が、兄「頼朝」と合流したのは、兄の平家討伐の富士川の戦いの直後でありました。兄弟は、平家一門を打ち、亡き父の無念を晴らすことを誓います。「弁慶」は人並はずれた老練、大力に加え、武術に秀でた人物と言われ、「義経」に従い源平合戦(1180-1185)に加わりました。
「義経」は平家滅亡に身をささげ、壇ノ浦の戦いで宿敵平家を壊滅し、悲願達成を果たした時、当然、兄「頼朝」からは長きにわたる辛い功労に対し労い(ねぎらい)の言葉があると思っていました。しかし、疑い深い「頼朝」は勝ち誇った「義経」が戻ってくるのを望みませんでした。日本で最初の武家政権「鎌倉幕府」を開いた「頼朝」ではありましたが、「義経」の鎌倉入りを許しませんでした。失意のどん底の「義経」は、「頼朝」に許しを請う書状(腰越状(こしごえじょう))を送りますが、結局は兄の敵意を強くさせるのみでした。「義経」は救いを、かつて若かりし時、一時身を寄せた奥州、藤原家に求めました。しかし当主「藤原秀衡」の死後、「頼朝」の圧力に屈した息子「泰衡」により自害を余儀なくされました。
驚くなかれ、今でも「義経」は日本人の中で人気のある歴史的英雄の一人であります。悲劇の英雄の象徴とされ、その死後でさえ、蝦夷(北海道)にいる、とかモンゴルに渡った、とか言ううわさ話が流れました。挙句の果てには、ジンギスカンと悲劇の英雄「義経」は同一人物である、という伝説まで生まれました。(2005.2.1 by Kudo/Image by Ohashi)



 五条の橋の上、小脇になぎなた(にほんのやり)を抱えた、一際大きな僧が、仁王のごとく、立っていました。明るい月が、五条の橋を照らし出していました。※なぎなた(幅広で反りの強い刀身に長い柄をつけた武器)
おや、大男の方へ、笛を吹き近づいて来る者がいます。何と美しい笛の音でしょう。薄での絹の着物を被いて(かずいて)いるのでその顔ははっきりわかりません。腰に差している太刀は由緒あるものに見えます。大男は、その立派な太刀に目をつけました。男は、笛吹きに向かって大音声を上げました。
「拙僧の宿願は千本の太刀を得ること。すでに999本の太刀を得た。あと一本で満願成就。」
しかし笛吹きは、一向に動じることなく笛を吹きながら、大男の脇を通り過ぎようとしました。
「おい、ちょっと待て。今も話したように、拙僧の宿願は千本の太刀。あと一本で満願成就だ。そちは見事な太刀を差しておる。それを拙僧に即座によこすなら、命は助けてやる。どこへなりと立ち去れ。」
その人は笛を吹くのを止め、被きものを取ります。何と気高い、きりりとした顔立ちの若者でしょう。
若者は、穏やかに、落ち着いた声で話します。
「そちが999本の太刀を集めたのは真実(まこと)か。しかし、そちがやっていることは盗みに他ならぬ。」
男は大声で叫びます。
「だまれ!お前が、太刀をよこさぬと言うなら、力ずくでも頂くまでだ。もうわしのものも同然だ。」
若者はおどしに動ずることなく、
「取れるものなら取ってみよ。」
男は、なぎなたを頭の上に振りかざし、若者を威嚇します。いつもなら、ここで大方の者は恐れをなし、太刀を捨てて逃げ出します。しかし、若者にその気配は全くなく、大男の攻撃をすばやくかわします。男のなぎなたが空を切ると、男はちょっと取り乱し、もう一度切りかかります。しかし若者を見失ってしまいます。
「一体どこに行った。」と怒鳴ります。
「ここぞ。御坊。」後ろから声がしました。
「何をこしゃくな!」
男は怒りで顔が真っ赤になり、再び切りかかります。若者は、今度は鳥のように軽やかに飛び上がり、笛で男のなぎなたを叩き落し、橋の欄干に立ちます。男は、慌てて、なぎなたを拾おうとしますが、その前に、若者はなぎなたの上に飛び降ります。
「容易にわが太刀は奪えぬと知ったか。」若者は男に言います。
「参った。降参だ。貴殿は、この道では、名の通るお方とお見受けした。お名前をお明かし下され。拙僧は弁慶と申す僧兵だ。」弁慶は、自らの負けを潔く認めて、「これからは、そこもとの郎党になりましょう。」と言う。
五条の橋の上、小脇になぎなた(にほんのやり)を抱えた、一際大きな僧が、仁王のごとく、立っていました。明るい月が、五条の橋を照らし出していました。※なぎなた(幅広で反りの強い刀身に長い柄をつけた武器)
おや、大男の方へ、笛を吹き近づいて来る者がいます。何と美しい笛の音でしょう。薄での絹の着物を被いて(かずいて)いるのでその顔ははっきりわかりません。腰に差している太刀は由緒あるものに見えます。大男は、その立派な太刀に目をつけました。男は、笛吹きに向かって大音声を上げました。
「拙僧の宿願は千本の太刀を得ること。すでに999本の太刀を得た。あと一本で満願成就。」
しかし笛吹きは、一向に動じることなく笛を吹きながら、大男の脇を通り過ぎようとしました。
「おい、ちょっと待て。今も話したように、拙僧の宿願は千本の太刀。あと一本で満願成就だ。そちは見事な太刀を差しておる。それを拙僧に即座によこすなら、命は助けてやる。どこへなりと立ち去れ。」
その人は笛を吹くのを止め、被きものを取ります。何と気高い、きりりとした顔立ちの若者でしょう。
若者は、穏やかに、落ち着いた声で話します。
「そちが999本の太刀を集めたのは真実(まこと)か。しかし、そちがやっていることは盗みに他ならぬ。」
男は大声で叫びます。
「だまれ!お前が、太刀をよこさぬと言うなら、力ずくでも頂くまでだ。もうわしのものも同然だ。」
若者はおどしに動ずることなく、
「取れるものなら取ってみよ。」
男は、なぎなたを頭の上に振りかざし、若者を威嚇します。いつもなら、ここで大方の者は恐れをなし、太刀を捨てて逃げ出します。しかし、若者にその気配は全くなく、大男の攻撃をすばやくかわします。男のなぎなたが空を切ると、男はちょっと取り乱し、もう一度切りかかります。しかし若者を見失ってしまいます。
「一体どこに行った。」と怒鳴ります。
「ここぞ。御坊。」後ろから声がしました。
「何をこしゃくな!」
男は怒りで顔が真っ赤になり、再び切りかかります。若者は、今度は鳥のように軽やかに飛び上がり、笛で男のなぎなたを叩き落し、橋の欄干に立ちます。男は、慌てて、なぎなたを拾おうとしますが、その前に、若者はなぎなたの上に飛び降ります。
「容易にわが太刀は奪えぬと知ったか。」若者は男に言います。
「参った。降参だ。貴殿は、この道では、名の通るお方とお見受けした。お名前をお明かし下され。拙僧は弁慶と申す僧兵だ。」弁慶は、自らの負けを潔く認めて、「これからは、そこもとの郎党になりましょう。」と言う。
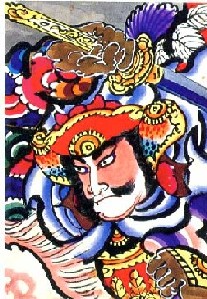 「私は牛若と申す。父、源義朝は源氏の棟領であったが、平治の乱で平家に滅ぼされた。いつの日か平家一族を倒したいと思っておる。それには私に仕える郎党が是非とも必要だ。そちにはわが郎党のかわきりになってもらおう。」
これは、「牛若」がその郎党となる「弁慶」に初めて出会った場面であります。後の源九郎判官義経(1159-1189)とは、この「牛若丸」でありました。「義経」が、兄「頼朝」と合流したのは、兄の平家討伐の富士川の戦いの直後でありました。兄弟は、平家一門を打ち、亡き父の無念を晴らすことを誓います。「弁慶」は人並はずれた老練、大力に加え、武術に秀でた人物と言われ、「義経」に従い源平合戦(1180-1185)に加わりました。
「義経」は平家滅亡に身をささげ、壇ノ浦の戦いで宿敵平家を壊滅し、悲願達成を果たした時、当然、兄「頼朝」からは長きにわたる辛い功労に対し労い(ねぎらい)の言葉があると思っていました。しかし、疑い深い「頼朝」は勝ち誇った「義経」が戻ってくるのを望みませんでした。日本で最初の武家政権「鎌倉幕府」を開いた「頼朝」ではありましたが、「義経」の鎌倉入りを許しませんでした。失意のどん底の「義経」は、「頼朝」に許しを請う書状(腰越状(こしごえじょう))を送りますが、結局は兄の敵意を強くさせるのみでした。「義経」は救いを、かつて若かりし時、一時身を寄せた奥州、藤原家に求めました。しかし当主「藤原秀衡」の死後、「頼朝」の圧力に屈した息子「泰衡」により自害を余儀なくされました。
驚くなかれ、今でも「義経」は日本人の中で人気のある歴史的英雄の一人であります。悲劇の英雄の象徴とされ、その死後でさえ、蝦夷(北海道)にいる、とかモンゴルに渡った、とか言ううわさ話が流れました。挙句の果てには、ジンギスカンと悲劇の英雄「義経」は同一人物である、という伝説まで生まれました。(2005.2.1 by Kudo/Image by Ohashi)
「私は牛若と申す。父、源義朝は源氏の棟領であったが、平治の乱で平家に滅ぼされた。いつの日か平家一族を倒したいと思っておる。それには私に仕える郎党が是非とも必要だ。そちにはわが郎党のかわきりになってもらおう。」
これは、「牛若」がその郎党となる「弁慶」に初めて出会った場面であります。後の源九郎判官義経(1159-1189)とは、この「牛若丸」でありました。「義経」が、兄「頼朝」と合流したのは、兄の平家討伐の富士川の戦いの直後でありました。兄弟は、平家一門を打ち、亡き父の無念を晴らすことを誓います。「弁慶」は人並はずれた老練、大力に加え、武術に秀でた人物と言われ、「義経」に従い源平合戦(1180-1185)に加わりました。
「義経」は平家滅亡に身をささげ、壇ノ浦の戦いで宿敵平家を壊滅し、悲願達成を果たした時、当然、兄「頼朝」からは長きにわたる辛い功労に対し労い(ねぎらい)の言葉があると思っていました。しかし、疑い深い「頼朝」は勝ち誇った「義経」が戻ってくるのを望みませんでした。日本で最初の武家政権「鎌倉幕府」を開いた「頼朝」ではありましたが、「義経」の鎌倉入りを許しませんでした。失意のどん底の「義経」は、「頼朝」に許しを請う書状(腰越状(こしごえじょう))を送りますが、結局は兄の敵意を強くさせるのみでした。「義経」は救いを、かつて若かりし時、一時身を寄せた奥州、藤原家に求めました。しかし当主「藤原秀衡」の死後、「頼朝」の圧力に屈した息子「泰衡」により自害を余儀なくされました。
驚くなかれ、今でも「義経」は日本人の中で人気のある歴史的英雄の一人であります。悲劇の英雄の象徴とされ、その死後でさえ、蝦夷(北海道)にいる、とかモンゴルに渡った、とか言ううわさ話が流れました。挙句の果てには、ジンギスカンと悲劇の英雄「義経」は同一人物である、という伝説まで生まれました。(2005.2.1 by Kudo/Image by Ohashi)
