 NHKゴガクトップ
NHKゴガクトップ- >英語のテレビ番組・ラジオ番組
- >ボキャブライダー on TV
ボキャブライダー on TV
言えそうで言えない英単語を紹介する語学コメディードラマの3rdシーズン。なぜか突然、目の前の人が外国人に変身し、英語で話し出すという事件が頻発。「紙詰まり」「門限」「裾上げ」。英語で言いたいのに、単語がわからない!そんなピンチを救ってくれるのが、スーパーヒーロー・ボキャブライダーの2人だ。英単語の語源やちょっとしたウンチクも満載!
放送時間
- 放 送:月曜日 午前5:45~5:50
再放送:火曜日 午後0:45~0:50
火曜日 午後7:50~7:55
木曜日 午後1:55~2:00
金曜日 午前10:50~10:55
金曜日 午後9:55~10:00
記載されている放送日時はあくまでも予定です。
詳しくは番組表でご確認ください。

番組で紹介した単語とミニ解説
![]()
![]() 11月11日放送 「傷つきやすい」
11月11日放送 「傷つきやすい」
- ● sensitive 「傷つきやすい」
- ● He is a bit sensitive. 「彼は傷つきやすいところがある」


解 説
日本語では「繊細で物事に感じやすい」という意味で「ナイーブ」を使いますが、英語でnaiveと言うと「うぶな、世間知らずの」といった意味になり、相手に面と向かっていうには適切な言葉ではありません。相手に対して「繊細なんですね」と伝えたいときにはsensitiveの方が無難です。
![]() 11月4日放送 「うっかり」
11月4日放送 「うっかり」
- ● slip 「うっかり」
- ● It slipped my mind. 「うっかりしてた」


解 説
“slip”は「するっと動く/なめらかに動く」というイメージの言葉です。日本語にもなっているスリッパ slipper(s)もこの言葉から派生した言葉です。さらにはこの“slip”は何かが「頭の中からするっとすべり落ちる」というイメージで使える言葉で、日本語の「うっかり」を表現するのにぴったりの言葉です。
![]() 10月28日放送 「門限」(5月6日の再放送)
10月28日放送 「門限」(5月6日の再放送)
- ● curfew 「門限」
- ● You used to have a strict curfew. 「昔は門限厳しかったよね」

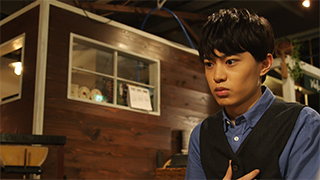
解 説
curfewという単語、「(夜間の)外出禁止令」という意味で覚えている人もいるかも知れません。現代では、英語ニュース等でその意味で登場することの多いcurfewですが、元はフランス語から来た言葉で“cover fire”、つまり“覆いをかぶせて火を消す”ということ。これは、中世ヨーロッパで、夜間の火災を防ぐため決まった時間に鐘を鳴らし、すべての火を消すという決まりがあったことに由来します。そこから、夜の訪れを告げる鐘、つまりは「晩鐘」という意味になり、それが発展して「門限・門限時間」、さらには「夜間外出禁止令」という意味になったと言われています。
![]() 10月21日放送 「人種差別」
10月21日放送 「人種差別」
- ● racial 「人種差別」
- ● I want to end racial discrimination. 「人種差別をなくしたい」


解 説
“race”には「急いで進む」「競争」「人種」と様々な意味がありますが、同音異義語です。その理由は語源の違いから来ており、スカンジナビア語源の“race”は「(人や動物が)急いで走る」という意味で、スコットランド語源だと「切り裂く」など、様々な言語を吸収して出来上がった英語の歴史が垣間見える単語です。「人種」という意味の“race”はイタリア語源と言われています。“discrimination”は「区別する」というラテン語から来た言葉です。「年齢による差別」なら“age discrimination”、「性別による差別」なら“gender discrimination”となります。
登場人物相関図
![]()

出演者開閉
テーマ音楽
「ボキャブライダーのテーマ」 作曲:平沢 敦士
































